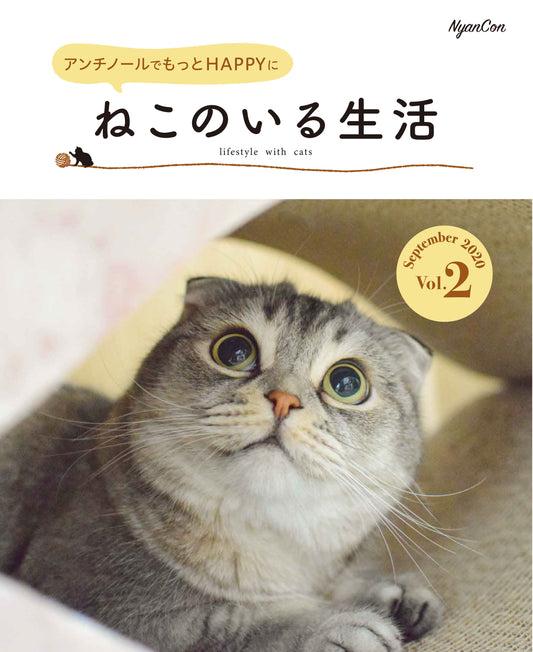【獣医師監修】猫の腎臓病で食べてはいけないものとは?避けるべき食材や食事の注意点

猫の慢性腎臓病では、病状の進行を抑えるために食事管理が重要です。また、健康な猫にとっては問題のない食事でも、慢性腎臓病の猫には悪影響となることがあります。
そのため、「腎臓病の猫に食べさせてはいけないものを知りたい」「食事管理をどうすべきか知りたい」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、慢性腎臓病の猫に食べさせてはいけないものや、食事管理の注意ポイントを詳しく解説します。なかなかご飯を食べてくれない時の対処法もお伝えしていますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 目次
-
腎臓病の猫が食べてはいけないもの
腎臓には、血液中の老廃物を取り除いて尿を作るという機能があります。この機能が低下すると、血液中に数十種類の尿毒素が溜まり、嘔吐や食欲不振等多くの症状を引き起こします。他にも、血圧や体液量の調整、ビタミンDの活性化など、健康維持のために重要な役割を担っています。
しかし慢性腎臓病にかかってしまうと、現在の治療法では腎機能を回復することはできません。そこで治療の中心は、食事療法による腎機能の保護と対症療法による生活の質(QOL)の維持に焦点が当てられます。
つまり慢性腎臓病の猫にとっては、食事がとても重要な治療となるのです。そこで、まずは慢性腎臓病の猫が健康な猫と同じように食べてはいけないものについて見ていきます。
たんぱく質
慢性腎臓病の猫は食欲不振になりますが、必要なエネルギー量は健康な猫と変わりません。食事量が落ちてエネルギー不足に陥ると、身体は筋肉中のたんぱく質を分解してエネルギーを補います。筋肉量が減ってしまうため、食欲が落ちた慢性腎臓病の猫にも健康な猫と同じエネルギー量が必要なのです。
完全肉食性の猫にとって、たんぱく質はとても重要なエネルギー源です。しかし同時に、尿毒素の元となる窒素老廃物を生成してしまうため、たんぱく質は腎臓病の進行を早める要因になってしまいます。
そこで、慢性腎臓病の猫の食事ではたんぱく質の摂取源と摂取量を制限します。窒素老廃物の生成を抑止し、病気の進行を抑えるのと共に、多尿の緩和も促します。科学的にも、たんぱく質を抑制した療法食は、慢性腎臓病の猫の生存日数を延長することが分かっています。
たんぱく質が豊富に含まれている食材で腎臓病に適している食材としては、鶏のささみや白身魚などが挙げられます。
リン
リンは骨や歯の主要な構成成分であり、体液のpH調整などにも関与している栄養素です。しかし腎機能の低下によりリン酸塩の排泄が阻害され、血中のリン濃度が高くなり(高リン血症)、食欲不振や吐き気等の症状が現れます。さらに進行すると、血液中のカルシウムと結合して血管や腎臓で石灰化を起こす、低下したカルシウムを骨から補って骨を脆くさせるといった悪影響を及ぼします。
これらを防ぐため、慢性腎臓病の療法食ではリンも制限します。リンを制限した療法食も、腎臓病の進行を抑制し、慢性腎臓病の猫の生存日数を延長することが分かっています。
リンが多く含まれている食材としては、牛乳・チーズなどの乳製品や肉類、魚介類、豆類が挙げられます。食品添加物にもリン酸塩が使用されているものが多いため、ソーセージ・ハムなどの食肉加工食品や清涼飲料水もリンの多い食材です。
ナトリウム
腎機能が低下すると、食物中から取り込んだナトリウムの濾過が追いつかなくなり、血液中にナトリウムが溜まって血中ナトリウム濃度が高くなります。身体はナトリウム濃度を下げようとして多くの水分を血液中に溜め込むため、血液量が増えて高血圧を招いてしまいます。
全身性高血圧は腎臓病の進行にも関与するため、ナトリウム制限による高血圧の抑制も、慢性腎臓病の猫の食事療法として必要な要素になります。
ナトリウムは、食品中では塩化ナトリウム(塩)の形で存在するため、塩分の高い食材は与えてはいけない食材になります。具体的には、ソーセージ・ハムなどの食肉加工食品、チーズ、鰹節、しらす干しなどです。基本的に人用に調理された食物は猫にとって塩分が多過ぎますので、注意が必要です。
腎臓病の猫が食べていいもの

特定の栄養素を制限するだけが、慢性腎臓病の食事療法ではありません。特定の栄養素については、健康な猫よりも積極的に摂取した方が良いものもあります。
この章では、慢性腎臓病の猫に積極的に食べさせた方がいいものについて解説していきます。
オメガ3脂肪酸
脂肪は食物のエネルギー密度を高め、かつ嗜好性を良くする効果を持つ栄養素です。健康な猫の場合は食べ過ぎて肥満を招く恐れがありますが、慢性腎臓病で食欲不振になり、たんぱく質を制限しながらも必要なエネルギーを摂取しなければならない猫にとっては、貴重な栄養素です。
中でもオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸を適切な比率で含むフードは、腎機能低下による高血圧を防止して腎臓病の進行を遅らせる効果が期待できます。ただし、いくら食べさせても良いというわけではなく、適切な量を守らなければなりません。慢性腎臓病の猫の食事としては、オメガ3脂肪酸の総量が乾物量当たり0.4〜2.5%、オメガ3:オメガ6の比率は1:1〜1:7の範囲が推奨値です。
オメガ3脂肪酸が多く含まれている食材としては、マグロ・イワシ・サーモンなどの魚類、アーモンド・胡桃などのナッツ類、亜麻仁油、エゴマ油などが挙げられますが、適切な量や他の栄養素とのバランスを考えながら与えるのは非常に困難なため、サプリメントや配合が強化された療法食などを与えるようにしましょう。
食物繊維
猫は肉食性の動物なので、基本的に植物性の食材を食べさせる必要はありません。しかし食物繊維を積極的に摂取させることで、腸内細菌叢の多様化による免疫力向上や代謝促進などの効果を期待できます。
食物繊維が豊富な食材はキャベツ・レタスなどの野菜やエリンギ・舞茸などのきのこ類ですが、猫にとっては消化しづらい食材なので、できるだけ少量を細かく刻んで与えるなどの工夫が必要です。
また慢性腎臓病の猫は、犬などの他の動物における高カリウムのリスクが注目されるのとは逆に、食欲不振による食事量の低下と多尿による水分喪失のために、低カリウムに陥ることが一般的です。そのため、健康な成猫の食事中のカリウムは乾物量当たり0.52%ですが、慢性腎臓病の猫には0.7〜1.2%と多めに食べさせることが推奨されています。
カリウムを多く含む食材としては、バナナ、ほうれん草、さつまいも、豆類、魚類、肉類などが挙げられます。バナナ、ほうれん草、さつまいもなどは、食物繊維と同様に、食べさせ方に工夫が必要です。また、野菜や果物には猫にとって禁忌の食材も多いため、事前によく確認した上で食べさせるようにしましょう。
腎臓病の猫の食事で注意すべきポイント

慢性腎臓病の食事は、治療の一環としての意味合いが大きいです。そのため独自の判断で用意した食事では、食事療法の効果を果たせず、せっかく併用している治療の効果も損ねてしまうかもしれません。
慢性腎臓病の猫の食事は、必ずかかりつけの獣医師と連携を取り、その時々の病状や猫の状態に合わせることが大切です。獣医師と連携をするためにも、あらかじめ飼い主さんに知っておいていただきたい基本的食事管理のポイントをご説明します。
食事療法ができるのは「療法食」のみ
慢性腎臓病の進行を抑えるためには、たんぱく質・リン・ナトリウムを制限し、オメガ3脂肪酸・食物繊維・カリウムなどを強化した食事が必要になります。
このような食事を市販の総合栄養食や一般食を組み合わせて用意することはとても難しいです。また、その時々の病態によっても調整が必要になることもあるでしょう。そのため、慢性腎臓病の猫に与える食事は、原則かかりつけの獣医師から処方された「療法食」に限定するべきだと考えましょう。
療法食は風味が限定されていて猫の食いつきが悪いというイメージがあるかもしれません。実際、療法食に切り替えた直後はあまり食べてくれないことも多いです。
しかし、腎臓病の療法食は複数のメーカーから、しかもさまざまなタイプや風味で販売されています。最初に処方された療法食の食いつきが悪くても、獣医師と相談しながら愛猫の好みと病態に合う療法食を見つけることができることがあります。食べない場合の対処法については後述します。
手作りごはんは非推奨
前述の通り、腎臓病用の療法食は健康な猫用の食事以上に栄養バランスを整えるのが困難で、手作りでバランスを適切な範囲に収めることは不可能に近いといっても過言ではありません。そのため、よほどの専門知識をお持ちの方でない限り、手作りでの療法食はおすすめできません。
市販の療法食ではどうしても食べてくれず必要なエネルギー量を確保できないという場合も、基本は療法食を利用し、かかりつけの獣医師と十分に相談をした上で、食べ方を工夫したり、サプリメントなど適切な補助食を用意することをおすすめします。
いずれにしても、かかりつけの獣医師との密な連携が必要です。自己判断による手作り食は、愛猫の病状を悪化させるリスクが高いことを覚えておいてください。
水分の摂取量も重要
健康な腎臓は尿を濃縮しますが、その機能がうまく働かないと薄い尿をたくさん排泄してしまいます。そのため、慢性腎臓病の初期症状は多飲多尿です。多尿は、体の水分を体外に排出し過ぎるため、脱水や腎血流の減少を招き、腎機能低下の進行を早めます。
しかも多飲多尿の症状が現れた時点で、腎臓の機能はすでに66%も低下していることが分かっています。そこで慢性腎臓病と診断された猫に大切なのが、十分な量の水分補給です。しかし、もともと猫は積極的に水を飲もうとする動物ではないため、水を飲ませるためにも工夫が必要です。
常に水を自由に飲めるよう複数箇所に水飲み場を設置した上で、こまめに水を取り替えることが大切です。また、流水式給水機の利用、冷水をやめてぬるま湯にする、味付けをしていない肉の煮汁にする、ウェットフードの利用などの工夫も、飲水量の増加に役立ちます。
困った時は獣医師へ相談
多くの場合、慢性腎臓病と診断されると食事療法だけではなく、定期的な通院による対症療法と経過観察も行うことになります。必然的に、獣医師に診察してもらい、飼い主さんが相談できる機会も増えます。慢性腎臓病の治療は完治を目指すものではなく、進行を抑え、生活の質を維持することが目的です。
そのため、食事療法に切り替えても効果が見られない、食欲不振が続いて思うように食べてくれないといった状態が続いたり、元気がなくなってきた、多飲多尿が進んた、えずいたり嘔吐したりなどの新しい症状が現れた場合などは、自己判断せずにできるだけ早くかかりつけの獣医師に相談しましょう。
進行すればするほど、猫は辛い思いをし、定期的な皮下補液などの治療も必要になってきます。愛猫の日々の様子や食事量、飲水量、排尿量などを記録し、少しの変化にも早期に気付いて獣医師に相談できるようにすることをおすすめします。
腎臓病の猫がごはんを食べないときの対策
療法食への切り替え時に最も悩ましいのが、食べてもらえないことでしょう。猫は、療法食に限らず今まで食べ慣れたフードと異なる風味や食感などの別のフードに切り替えるのが難しい動物です。いきなり療法食を出しても、ニオイを嗅いだだけで口をつけない猫がほとんどでしょう。
療法食に切り替える場合は、従来のフードと療法食の双方を混ぜて与えるようにすることをおすすめします。1日に1割程度ずつ療法食の量を増やしていくようにして、おおよそ10日程で完全に切り替えることを目安に、愛猫の様子を見ながら調整していきましょう。
給餌方法は、同じお皿に混ぜて入れても別々のお皿に分けて入れても構いません。同じお皿に混ぜて入れると食べない場合は、2皿に分けてみてください。最初は従来のフードしか食べないかもしれませんが、日が経ち従来のフードの量が減ってくると、お腹が空いて療法食も食べるようになることがあります。
また、ドライフードの場合はぬるま湯でふやかしてニオイを引き立たせたり、ウェットタイプの療法食を利用したりすることでも、食いつきが良くなることがあります。こういった工夫だけではどうしても食べてくれない場合は、獣医師に相談しましょう。場合によっては、食欲増進剤を使用したり、強制給餌を行う場合もあるかもしれません。
腎臓病の猫の食事についてよくある質問

最後に、慢性腎臓病の猫に与える食事に関するよくある質問をまとめました。慢性腎臓病の愛猫に与える食事について悩んでおられる飼い主さんは、ぜひ参考になさってください。
腎臓病の猫におやつを与えても良い?
ここまでご説明してきた通り、慢性腎臓病の猫への食事は、特殊な栄養バランスでしっかりとエネルギーを補給することが必要になるため、安易におやつを与えてしまうことはあまりおすすめできません。
しかし、ご褒美としておやつを使いたいなど、どうしてもおやつを与えたい場合もあるでしょう。その場合は、腎臓病用として市販されているおやつを獣医師との相談のうえで可能であれば利用しましょう。
たとえ少量だからといって、人用の食べ物や一般食のおやつを与えると、リン、ナトリウム、たんぱく質などの量が過剰となり、腎機能低下を促進させてしまいますので注意してください。
腎臓病用のフード(療法食)でないとだめ?
かかりつけの獣医師から慢性腎臓病用の療法食を処方された場合は、原則として療法食を与えてください。特別療法食を腎臓病の猫に給与することで腎臓病の進行を抑制したというエビデンスもあります。従来通りの総合栄養食では、腎機能の低下を促進してしまうリスクが高く、また療法食に相当する栄養バランスの食事を手作りで用意するのは、一般的な栄養学の知識だけでは至難の業です。
慢性腎臓病は進行性の病気で、現状では、失われた腎機能は二度と回復できません。適切な栄養バランスの療法食で、できるだけ残っている腎機能を保護することしかできないのです。そう考えれば、間違いなく適切な食事を与えられる療法食の利用が、愛猫に対してできる最善の手段だと言えるでしょう。
サプリメントを与えても良い?
サプリメントは、適切な成分を選べば腎臓の健康維持に役立つ可能性があります。
代表的な成分には「吸着・排出サポート成分」「乳酸菌類」「オメガ3脂肪酸」があり、リンの蓄積防止や腸内環境の改善、炎症の抑制、血流改善などが期待されます。
ただし、すべての猫に適しているわけではないうえに、薬との相互作用にも注意が必要です。
安全性の高いサプリメントを選ぶためには、動物病院で取り扱われているものや、成分の含有量が明確なものを選ぶことが重要です。また、食欲が低下しがちな猫には食べやすい形状のものを選ぶと良いでしょう。
サプリメントはあくまで補助的なものであり、腎臓病を治療するものではありません。療法食や適切な医療ケアを中心に、獣医師と相談しながら適切に活用することが大切です。
まとめ 猫の腎臓病は食事内容が重要
慢性腎臓病は、猫の宿命とも言われる程多くの猫がかかる病気です。そして現状、一度発症したら治ることはなく、進行していくだけです。猫が若い頃からしっかりと健康管理を行い、定期的に健康診断を受けさせることで、腎機能低下を早期に発見しましょう。そうすれば、初期の段階で食事療法を開始できます。
また慢性腎臓病は、発症してから愛猫を看取るまで、長く治療を続けなければならない病気でもあります。どうか飼い主さんが根負けしてしまうことなく、かかりつけの獣医師と連携しながら適切な食事療法を続けてあげられるよう、頑張ってください。
- 監修者プロフィール
-
岩谷 直(イワタニ ナオ)
経歴:北里大学卒業。大学研修医や企業病院での院長、製薬会社の開発や学術職などを経て株式会社V and P入社
保有資格:獣医師免許