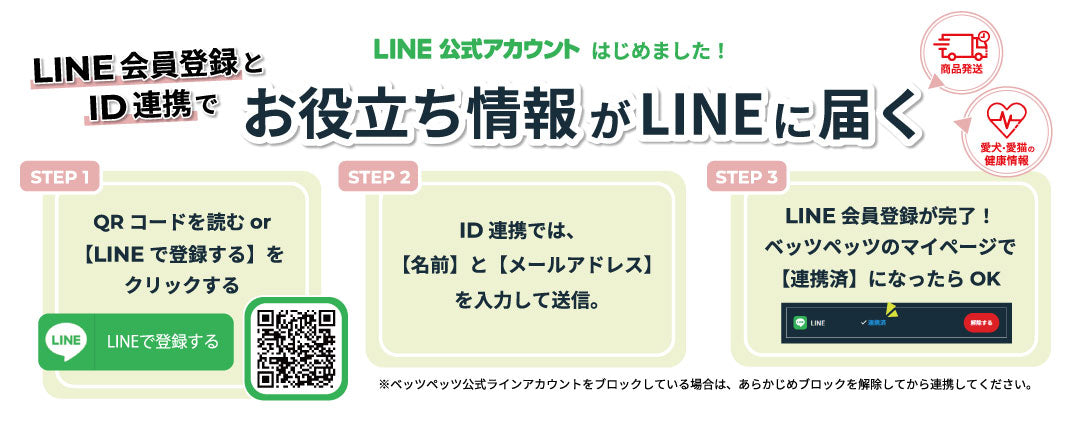【獣医師監修】犬のアトピー性皮膚炎の症状・原因とは?治し方や治療費についても解説

犬のアトピー性皮膚炎は、常に激しい痒みが伴うため、愛犬の生活の質(QOL)を著しく悪化させる病気です。そのため、「少しでも愛犬の生活の質を良い状態に維持させたい」と悩まれている飼い主様も多いでしょう。
そこで犬のアトピー性皮膚炎の症状や原因、診断、治療法や予防法について解説します。正しい知識を身につけた上で、かかりつけの獣医師と相談して、愛犬の生活の質を維持させられるような最適なケアを見つけましょう。
- 目次
-
犬のアトピー性皮膚炎とは
犬のアトピー性皮膚炎とは、アレルギー反応により起こり、犬によく見られる皮膚疾患です。通常、動物の体は細菌やウイルスなどの有害な病原体をアレルゲンと認識し、免疫反応を引き起こすことで身体から排除します。しかしアトピー性皮膚炎の場合、花粉やハウスダストなどの環境中に存在する本来は無害な物質を、排除すべきアレルゲンとして誤って認識し、過剰に免疫反応を引き起こしてしまいます。
主な症状は慢性的なかゆみと炎症です。特にかゆみは、飼い主様が制止すれば一時的に掻くのをやめられるものの、かゆみで眠れなくなったり、食事や散歩の途中でも掻かずにはいられなくなったりと、日常生活に支障をきたすレベルのものもあります。
このため、犬のアトピー性皮膚炎は、愛犬の生活の質を低下させる病気の一つだと言えます。
犬のアトピー性皮膚炎の症状
犬のアトピー性皮膚炎の主な症状は、慢性的に続く中等度から重度のかゆみと炎症です。特に、皮膚病変に先立ってかゆみが現れるのが特徴的です。アトピー性皮膚炎における皮膚の症状は、下記のように段階的に進んでいきます。
-
アレルゲンの侵入
環境中のハウスダストマイト、花粉などが皮膚バリアを通じて侵入
-
かゆみの出現
アレルゲンに対する免疫応答によりヒスタミンなどが放出され、かゆみが誘発
-
発赤、発疹
掻きむしりや炎症により皮膚に赤みや小さな盛り上がりが見られる
-
皮膚の変性
慢性的な掻きむしりで皮膚が黒ずんだり(色素沈着)、厚く硬くなる(苔癬化)
-
びらん・潰瘍などの重度病変
さらに掻きむしることで皮膚がただれたり、えぐれるような病変が形成される
初めにかゆみが生じ、掻くことで発疹が現れ、掻き続けることで皮膚が変性していきます。この過程で、掻きむしった部分の脱毛も見られます。ただし、かゆみを適切に管理し犬の掻き行動を抑えることができれば、症状の進行を防ぐことも可能です。
また犬のアトピー性皮膚炎は、症状が現れる部位についても「左右対称に分布する」という特徴が見られます。個体差はありますが、特に症状が現れやすい部位は皮膚が薄くなっている部分、皮膚同士が重なっている部分、お腹側です。具体的にいうと、顔(目、鼻、口の周辺)、耳、首の内側、胸、お腹、脇、股、足先になります。特に顔、首の内側、足先に症状が出やすい傾向があるとされています。
犬のアトピー性皮膚炎の原因

犬のアトピー性皮膚炎は、発症の原因や進行に関与する要因が複数あり、それらが互いに影響しています。そのため、初期段階のかゆみを適切に管理するためにも、愛犬がアトピー性皮膚炎を発症した原因や背景を正しく知ることが大切です。
この章では、犬のアトピー性皮膚炎の原因や背景となる要素の中から、特に飼い主様に知っておいていただきたい下記の3点について詳しく見ていきます。
-
遺伝的な要因
-
アレルギー反応
-
皮膚のバリア機能低下
遺伝的な要因
犬のアトピー性皮膚炎の背景には、遺伝的な要因が潜んでいることが多いです。アトピー性皮膚炎になりやすい体質が、親から子へ、子から孫へと引き継がれていくのです。
犬は特定の遺伝子を固定してさまざまな犬種を作出するため、犬種によってアトピー性皮膚炎を発症しやすい犬種とそうでない犬種があります。遺伝的要因により特定の病気を発症しやすい犬種を「好発犬種」と言います。犬のアトピー性皮膚炎の好発犬種には、下記の犬種が挙げられます。
-
柴犬
-
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア
-
シー・ズー
-
パグ
-
ボストン・テリア
-
フレンチ・ブルドッグ
-
ミニチュア・シュナウザー
-
ラブラドール・レトリーバー
-
ゴールデン・レトリーバー
-
ヨークシャー・テリア
-
ワイヤーヘアード・フォックス・テリア 等
アレルギー反応
アトピー性皮膚炎の発症には免疫反応の一種であるアレルギー反応が関与しています。
動物には、自分の体を守るための免疫機構が備わっています。体内に侵入した病原体を攻撃して健康を守る仕組みが免疫機構です。しかしこの免疫機構が、病原体以外の物質に誤って過剰に反応してしまうことがあり、これをアレルギー反応、誤認識された物質をアレルゲンと言います。
アトピー性皮膚炎の場合、ハウスダストや花粉といった、環境中に浮遊している物質がアレルゲンとなります。ハウスダストの正式名称はハウスダストマイトで、日本語訳は室内ダニです。埃ではなく、埃の中に紛れている室内ダニがアレルゲンとなるのです。
室内のこまめな掃除や散歩から帰宅した後の全身の拭き取りといった衛生管理が、愛犬をアレルゲンから守ることにつながることもあります。
皮膚のバリア機能低下
皮膚は、感覚器として温度、痛み、かゆみなどを感じる、体温を調整するなど、さまざまな役割を担っています。中でも重要なのが、外敵の侵入を防ぐ「バリア機能」です。
何らかの原因によって皮膚のバリア機能が低下すると、アレルゲンが体内に侵入しやすくなり、アトピー性皮膚炎を発症しやすくなるのです。皮膚の最も外側となる表皮は、角質細胞がブロックを積み重ねたような構造をしており、セラミド、コレステロールエステル、遊離脂肪酸などの脂質が細胞同士をつなぎとめています。
この角質細胞や脂質が不足することで皮膚のバリア機能が低下し、アトピー性皮膚炎をはじめとしたさまざまなアレルギー性皮膚疾患が発症しやすくなると考えられています。栄養バランスの取れた食事と適切な運動で愛犬の健康を維持することは皮膚の健康にも影響を与え、その結果、皮膚のバリア機能の低下予防にもつながります。
また、アトピー性皮膚炎の多くの場合、皮膚の水分の蒸散量が増加し、ドライスキンになっていることが特徴です。ドライスキンはますます痒みを引き起こし、掻きむしりによる炎症で皮膚のバリア機能が低下する、という悪循環に繋がります。皮膚を保湿するスキンケアも非常に重要になってきます。
犬のアトピー性皮膚炎の診断方法
獣医師は、診察の際の問診(飼い主様からの情報提供)、犬への触診、聴診や各種の検査から得た情報により、多くの病気の可能性を一つずつ除外していきます。そして、最終的に残った病名を確定するための検査等を経て、診断を下します。
アトピー性皮膚炎と似た症状を見せる病気には、ノミやダニ等の外部寄生虫の感染症、ブドウ球菌やマラセチア菌等の常在菌の増殖、食物アレルギーなどが挙げられます。これらの除外診断を進めながら、アトピー性皮膚炎の特徴を確認することで、最終的な診断を確定します。
一般的に、犬のアトピー性皮膚炎を診断する指標として信頼性の高い臨床診断基準が提唱されており、下記の特徴が見られるかを確認します。
-
初発時期が3歳以下である
-
主に室内で生活している
-
ステロイド剤の投与によりかゆみが改善される
-
マラセチア菌が検出されやすい
-
前肢に症状がある
-
耳介外側に症状がある
-
耳介辺縁に症状がない
-
背から腰にかけて症状がない
これらの特徴のうち5つ以上を満たすと、非常に高い信頼性でアトピー性皮膚炎と診断できるとされています。
アトピー性皮膚炎だと診断が確定した場合、必要に応じてアレルゲンを推定するための検査を行う場合もあります。
犬のアトピー性皮膚炎の治し方

アトピー性皮膚炎は、アレルゲン自体が直接症状を引き起こすわけではなく、自分自身の免疫機構が過剰に反応することで発症するため、完治させるのが難しく、生涯にわたる管理が必要となる病気の一つです。治療の目的は、かゆみによる影響をできる限り抑えて、日常生活における生活の質(QOL)を良好に維持することになります。
以下のような治療やケアを行うことで、かゆみのコントロールや症状の改善を図ることで、愛犬の生活の質をできるだけ高く維持させることを目指します。
-
投薬による治療
-
適切なスキンケア
-
生活環境の見直し
投薬による治療
犬のアトピー性皮膚炎の特徴は、まずかゆみが発生し、犬がかゆみのために掻きむしることで発疹や発赤が生じ、症状が徐々に進行していくことです。このかゆみを適切に管理し、犬の掻きむしりを抑えることが、治療の鍵となります。
かゆみや炎症を抑える治療として効果が期待できるのが、ステロイド薬の投与です。他にも、症状や体質に応じて、免疫抑制剤、分子標的薬、抗ヒスタミン剤、インターフェロン-γ等を選択する場合もあります。また、アトピー性皮膚炎では細菌などによる二次感染がみられる事もありますので、必要に応じて抗生剤などを使用することがあります。
ステロイド薬は長期的な使用で副作用が見られやすいですが、即効性とかゆみを抑える効果は非常に高いため、治療開始時に短期的に使用されることがあります。ステロイドによりかゆみや炎症が改善された後に他の薬剤への切り替えや他のスキンケアとの組み合わせで良好な皮膚の状態を維持することが理想的な治療とされています。
脂肪酸サプリメントの給与や、腸活によってアトピー性皮膚炎の管理に役立ったというデータもありますので、獣医師と相談しながら、上手に取り入れていくのもよいでしょう。
またアレルギー検査によりアレルゲンが同定された場合には、低濃度のアレルゲン抽出液を注射で投与していくことで体質改善を図る、減感作療法を選択する場合もあります。減感作療法はアレルゲンの種類により実施可能な病院が限定される場合があります。
適切なスキンケア
アトピー性皮膚炎の犬は皮膚バリア機能が低下していることが多いため、そのことを理解せずに誤ったスキンケアを行ってしまうと、症状の悪化につながります。ご自宅でアトピー性皮膚炎の犬のスキンケアを行う場合は、下記の点に注意しましょう。
①低刺激性のシャンプーを選ぶ
アトピー性皮膚炎の犬には、皮膚への刺激が少なく、保湿効果のあるシャンプーが推奨されます。例えば、セラミドを含むシャンプーは、皮膚バリアの機能をサポートします。
②保湿ケアを欠かさない
シャンプー後は、皮膚が乾燥しやすくなるため、保湿剤の使用が必須です。セラミドなどの保湿成分を含むローションやスプレーを使用することで、皮膚の水分保持力を高め、バリア機能を強化できます。
③シャンプーの頻度を調節する
皮膚の状態に応じて、シャンプーの頻度を調節することも重要です。シャンプーは余分な皮脂やアレルゲンを取り除くという意味では重要ですが、皮膚のバリア機能を破壊するリスクがあります。頻度が多ければよいということでもなく、犬や飼い主様の負担も大きくなるので、週1回または2週に1回程度など、皮膚の状態に合わせて獣医師と相談しながら調節しましょう。
④洗浄時の注意点
・お湯の温度:熱すぎるお湯は皮膚を刺激するため、ぬるま湯を使用しましょう。
・ドライヤーの使用:シャンプー後は、清潔なタオルで十分に水分を拭き取り、ドライヤーで乾かします。ただし、ドライヤーの熱が皮膚に直接当たらないように注意が必要です。
ただし、症状によって必要な洗浄力や頻度などは異なります。飼い主様が独断で判断するのではなく、必ずかかりつけの獣医師と連携しながら、適切なスキンケアを行うことが大切です。
生活環境の見直し
犬のアトピー性皮膚炎は、治療によるコントロールが生涯必要となる病気です。そのため、生活環境やライフスタイルの見直しも、症状の管理において重要な役割を果たします。アレルゲンをできるだけ排除する、そして皮膚のバリア機能低下を防ぐことに着目し、下記の観点で生活環境やライフスタイルの見直しを行ってみてください。
室内のこまめな清掃によるハウスダストやダニの排除
おもちゃ等の定期的な洗浄
外出時の洋服着用によるアレルゲン付着量の抑制
帰宅後の全身拭き取りによるアレルゲンの除去
栄養バランスの取れた食事と適切な運動による健康管理
室内の湿度を40~60%に保つことで皮膚の乾燥やカビの発生抑制
規則正しい生活や飼い主様との適切なコミュニケーションによるストレスのない生活
犬のアトピー性皮膚炎の治療費
アトピー性皮膚炎を発症すると、生涯にわたり定期的な通院と治療が必要になります。そこで気になるのは、どの程度の治療費が必要になるのかということではないでしょうか。
動物病院の診療費は、人の医療でいう自由診療にあたるため、初診料や診察費、検査費などは動物病院がそれぞれ独自に設定しています。また必要な薬の量も、体重によって異なりますし、アレルギー検査などを行う場合は別途検査費用が必要になります。
しかし一般的な相場を想定した場合、アトピー性皮膚炎の治療は1回の通院につき3,000円〜10,000円程度です。通院頻度を月に2回と想定した場合、単純計算で年間の治療費は72,000円〜240,000円程度、症状の悪化などがある場合はそれ以上かかることが見込まれます。
決して安い費用ではありませんが、愛犬を家に迎え入れた時からペット保険への加入を検討をすることも、解決策の一つになるでしょう。
犬のアトピー性皮膚炎の予防法

ここまでご説明してきたように、アトピー性皮膚炎は直接発症の引き金となる病原体があるわけではなく、遺伝的背景や免疫機構の過剰反応などが関与しているため、完全に予防する方法や薬はありません。
そのため、発症後に治療で改善した状態を維持することが、予防の役割を果たします。具体的には、下記の観点による管理が予防法として効果を期待できます。
-
アレルギー物質を避ける
-
適度にシャンプー、保湿をする
-
スキンケアフードに変える、あるいはサプリメントを併用する
アレルギー物質を避ける
アレルギー反応を引き起こすアレルゲンを避けることが、最も効果の期待できる予防法になります。治療法の「生活環境の見直し」と重複しますが、症状の改善後も、継続してアレルゲンを遠ざけるような環境維持を心掛けましょう。
日常的にアレルゲンを避けるためには、下記を意識しましょう。
-
室内は常日頃からこまめに掃除機をかける
-
花粉がアレルゲンの場合、飛散ピーク時の散歩では洋服を着用させる
-
季節にかかわらず、帰宅後には愛犬の全身を拭き取る
-
必要に応じて空気清浄機を導入する
適度にシャンプーする
犬のアトピー性皮膚炎の症状を悪化させないためには、症状の改善後も皮膚や被毛を清潔な状態に維持することが大切です。治療による症状改善後のシャンプーとしては、下記の手順が一般的に推奨されています。かかりつけの獣医師に相談しながら、適切なシャンプー剤や保湿剤を選び、適切な頻度で症状の再発や悪化を予防しましょう。
-
ブラッシング、コーミング
フケや埃、毛玉などを取り除く
-
すすぎ
35℃前後のぬるま湯で皮膚と毛を十分に濡らす(5〜15分程度の入浴も可)
-
シャンプーの準備
少量の水とシャンプーを混ぜ、スポンジなどで十分に泡立てる
-
シャンプー
泡立てたシャンプーを皮膚や毛に塗布し、毛の流れに沿って揉み込む
-
すすぎ
シャンプーが皮膚や毛に残らないよう、ぬるま湯でしっかりとすすぐ
-
保湿
皮膚や毛の水分を切り、保湿剤を全身に塗布する
-
ドライイング
バスタオルとドライヤーでしっかりと水分を除去する
スキンケアフードに変える
主食として良質な総合栄養食を与えている場合は、食事が原因で皮膚のバリア機能が低下する心配はほぼありません。しかし、アトピー性皮膚炎を発症している犬は、食物にもアレルギーを持っている場合が多く見られます。
食物アレルギーの原因となりやすい食材には、牛肉、乳製品、鶏肉、小麦などがあります。これらの食材を使わない、低アレルギーの食材を主原料としたアレルギー対策ドッグフードも市販されています。そのため、食物アレルギーもある場合は、獣医師と相談した上で、こういったフードに切り替えることも症状改善や予防法の選択肢に入ります。
また、犬のアトピー性皮膚炎のかゆみを管理するための補助療法として、セラミドなどの皮膚バリア機能に関与する脂質を補充できる必須脂肪酸のサプリメントもあります。かかりつけの獣医師とよく相談した上で、こうしたサプリメントの利用を検討するのも良いでしょう。
まとめ 犬のアトピーは自宅ケアも大切
犬のアトピー性皮膚炎は、遺伝的背景や免疫機構の関与が強く、完治が難しい病気です。そのため、生涯にわたって定期的な通院と治療による管理が必要になります。また治療により症状の改善が見られた後も、自宅でのケアや症状の再発、悪化を防ぐための予防を続けることが大切です。
本記事でご紹介した環境の整え方やシャンプーの方法なども参考にしていただき、かかりつけの獣医師と相談し、愛犬の生活の質を少しでも高く保てるよう、適切に管理してあげましょう。
- 監修者プロフィール
-
岩谷 直(イワタニ ナオ)
経歴:北里大学卒業。大学研修医や企業病院での院長、製薬会社の開発や学術職などを経て株式会社V and P入社
保有資格:獣医師免許