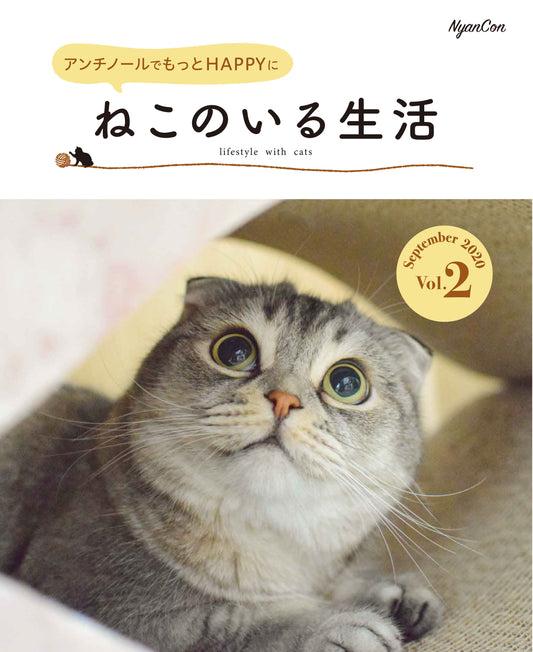【獣医師監修】猫の腎臓病を予防する6つのポイント!サプリやフードについても

猫の腎臓病は、比較的発症確率の高い病気です。若い時でも発生する急性腎障害と、高齢な猫に多く見られる慢性腎臓病の2つに分類できます。特に慢性腎臓病は、完治を期待できない病気であるため、健康な頃から予防に努めることが大切になります。本記事では、猫の腎臓病の予防について、詳しく解説します。
- 目次
-
猫の腎臓病とは?
腎臓は、腰の辺りの背中側にあり、背骨を挟むように2つ並んでいる臓器です。腎臓は、ネフロンと呼ばれる腎小体とそれに続く尿細管の組み合わせを1つの単位として、それが複数集まって構成されています。人の腎臓は1つが100万個、猫は20万個のネフロンで構成されています。
腎小体では、腎臓に流入した血液から代謝産物などの老廃物や毒素をろ過して取り除き、きれいになった血液を戻します。そして取り除いた老廃物等を尿の原液として尿細管に送り出します。尿細管では、一緒に取り除かれてしまった必要な栄養素を再吸収したり、体のバランスを保つために必要なホルモンを分泌したりしながら尿を作り、腎臓に続く尿管へと送り出します。
腎臓病は、この機能が何らかの原因で阻害される病気です。短期間の間に急激に大きなダメージを受けるのが急性腎障害、長い時間をかけて少しずつ腎臓の機能が低下していくのが慢性腎臓病です。
腎臓が機能しなくなると、体内に不要な老廃物や毒素が残ってしまうため、急性腎障害でも慢性腎臓病でも、最終的には愛猫の命に関わる病気だということに変わりはありません。
猫の腎臓病はなぜ予防が大切なのか
急性腎障害は進行が早くダメージも大きいため、すぐに適切な処置をしなければ命に関わる事態になりかねない病気です。また慢性腎臓病は、進行が非常に遅くなかなか症状が現れないため、気付いた時にはすでにかなり進行しているケースがほとんどです。さらに、慢性腎臓病で機能を失ったネフロンを治療で再生することはできません。一度発症したら、生涯にわたって治療を続けなければならないのです。
そのため、若い頃から予防を意識したケアを行うことが重要となります。急性腎障害の原因の約60%は毒物や薬物の誤食、約30%が感染、約10%が腫瘍だという報告が示す通り、急性腎障害には明確な予防策もあります。
急性腎障害が回復した後に慢性腎臓病に移行するケースや、加齢によるネフロンの機能低下、歯周病菌による影響などが原因だとされている慢性腎臓病の場合も、急性腎障害の予防や日々のデンタルケア、そして日頃から腎臓の負担をできるだけ軽くするように心がけることが予防になると考えましょう。
それでは、次の章で具体的に予防のポイントを見ていきます。
猫の腎臓病を予防する6つのポイント

まだ猫が若くて健康な段階から、腎臓にかかる負担をできるだけ軽減する、腎臓に対して毒性を発揮するものを猫に誤食させない、心身ともに健康な生活を心がけることで高い免疫力を維持させるといった観点で腎臓病を予防することができます。以下に挙げる予防のための6つのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
-
水分摂取を促す
-
排尿をしやすい環境を整える
-
ストレスを与えないようにする
-
遊ぶ時間を確保する
-
腎臓毒性物質を避ける
-
バランスの良い食事を与える
水分摂取を促す
体内に必要な水分量が不足した状態を脱水状態と言います。脱水状態になると、腎臓に高い負荷がかかります。水の少ない環境で暮らしていた祖先を持つ猫は、濃い尿を作ることで体内の水を有効利用するようにできていますが、腎機能が低下すると濃い尿を作れなくなり、脱水症状が進んで悪循環に陥ります。そのため、普段から猫に必要十分な水を飲めるような環境を整えることが腎臓病の予防に役立ちます。
猫は元々あまり水を飲もうとしないため、下記の点に配慮することで、猫の飲水量を増やすことができます。愛猫に合わせて、効果のある対策をみつけましょう。
-
1日に数回水を取り替えて新鮮さと清潔さを保つ(器は毎回洗う)
-
猫がよく行く複数の場所に水を設置する
-
好みの水(冬のぬるま湯や夏の冷水、調味料不使用の肉や魚の茹で汁、とろみつけ等)
-
好みの器(流水式、高さ、口径、材質等。ひげが当たるのを猫は嫌がります)
-
ウェットフードの割合を増やす
-
特にシニア猫の場合、流動食を活用して食事からの水分補給に重きを置くのも良い
排尿をしやすい環境を整える
猫はとても繊細な面を持っており、ちょっとしたことでもストレスに感じて排尿を我慢してしまうことがあります。排尿ができないことで、急性腎障害の原因となる尿路結石や膀胱炎などが発症しやすくなるため、排尿しやすい環境を整えることも腎臓病の予防につながります。
猫は落ち着ける環境にある清潔なトイレでの排泄を好みます。下記の点に配慮しながら、愛猫に適した環境を整えてあげましょう。
-
猫が入りやすい形状で体長の1.5倍以上の広さとある程度の深さがあるトイレ
-
猫の頭数+1個のトイレを用意
-
猫が好む材質や大きさの猫砂
-
食事場所や寝床から2m以上離れた静かで落ち着ける場所にトイレを設置
-
排泄物のこまめな片付け
-
定期的な猫砂の交換とトイレ本体の掃除
ストレスを与えないようにする
急性腎障害の原因にもなり得る膀胱炎は、感染症が原因になることもあります。しかし猫の膀胱炎の多くは、感染性ではなく、ストレスが原因となっている特発性膀胱炎であるケースが多いと言われています(報告では、特発性が60~70%、細菌性は10%未満とされています)。膀胱炎は尿路結石や尿路感染症へとつながることも多いため、ストレスの少ない環境を整えることも、猫の腎臓病の予防につながります。
猫のストレスを排除するためには、猫が本来持っている習性と猫の性格をよく理解することが欠かせません。下記の点に配慮をしながら、愛猫に適したストレスのない環境を整えましょう。
-
リフォーム、模様替え、引っ越しなどの大きな環境変化をできるだけ避ける
-
環境に変化が生じた場合、猫のニオイがついた毛布、寝床などを置いて安心させる
-
雨戸や防音窓等で、屋外からの騒音をできるだけ緩和させる
-
来客時などに猫が隠れられる安全な居場所を複数箇所に作る
-
棚の上を開放やキャットタワーの設置等で、空間を立体的に利用させる
-
窓の外を見られるようにする、知育玩具を与える等で、留守番時も退屈させない
遊ぶ時間を確保する
どんなに環境を整えても、猫のストレスを完全に排除することはできません。そこで、積極的に猫にストレスを発散させることも大切です。
飼い主様が毎日猫じゃらしなどのおもちゃを使って愛猫と一緒に遊ぶことで、適度な運動をさせられ、飼い主様との関係も深められます。遊ぶことで猫が持っている狩猟欲求を満たすことができるため、遊ぶ時間を確保することは猫のストレス発散となり、特発性膀胱炎の予防にも役立ちます。また体を動かすことで、万病の元となる肥満も予防できます。
下記の点に配慮しながら、愛猫が好む遊びを見つけましょう。
-
猫の遊びは、狩ごっこが基本形であることを理解する
-
おもちゃを獲物に見立てて飼い主様が上手に動かし、猫に狩りをさせます
-
猫は持久力がなく高い瞬発力を持つため、1回の遊び時間は15分程度で十分
-
1日に数回、できれば食事の前に狩りごっこで遊ぶ時間を作ると良い
腎臓毒性物質を避ける
急性腎障害の予防として何よりも大切なことは、猫の手の届く範囲に腎臓毒性のあるものを置かないことです。
猫が中毒を起こす可能性のある食べ物や薬剤、植物は、意外と私たちの身近に溢れています。中毒を引き起こすリスクを排除するため、猫の生活圏内には置かない、放置しない、飾らないことを徹底しましょう。
猫に中毒を引き起こす可能性のあるものには、下記のようなものが挙げられます。
-
ユリ科の植物
花、葉、茎、花粉などに毒性成分が含まれるため、室内に飾らない
花瓶の水も口にさせない
-
人の医薬品、不凍液、ネギ類・ブドウ・アボカド・甲殻類等の猫に禁忌な食材
開けられない引き出し等に保管する
バランスの良い食事を与える
良質で栄養バランスの良い食事は、腎臓病に限らず猫の健康を維持するためには大切です。若くて健康な頃から、愛猫の年齢やライフステージに合わせて、良質で栄養バランスの取れた食事を与えるように心掛けましょう。
最近は、ウェットタイプの総合栄養食も市販されていますので、水分補給も考慮して双方のフードを上手に組み合わせることで、腎臓への負担を軽減できる場合もあります。
また、愛猫の健康診断で腎機能の低下傾向が見られたり、多飲多尿といった初期症状が現れた場合は、老廃物を体に溜まりにくくすることに配慮した、タンパク質・ナトリウム・リンを制限した療法食による食事療法を始めることが多いです。
かかりつけの獣医師と相談しながら、その時の病態に適しており、かつ猫が好んで食べてくれる風味の療法食を見つけて、腎臓への負担を軽減するように栄養面からの管理も行いましょう。食事療法が始まったら、おやつも含めて総合的に管理することが大切です。
なお、一般職から療法食へ切り替える際には、今までのフードに療法食を少しずつ混ぜながら段階的に切り替えていく方法がおすすめです。
猫の腎臓病予防では健康チェックも重要

慢性腎臓病の初期症状である他院多尿が見られる段階では、2つある腎臓を合わせてもすでに正常なネフロンが約33%程度しか残っていない状態であることが報告されています。そのため、愛猫の変化に少しでも早く気付けることが、病気の早期発見につながり、病気の進行を遅らせたり、症状への適切な対処で猫の負担を軽減することができます。
そのためには、常日頃から愛猫の健康状態をチェックする習慣を付けることが大切です。下記の観点で、愛猫の健康状態をチェックするコツをご紹介します。
-
定期検診を受ける
-
飲水量や排尿量、排尿回数などを記録する
定期検診を受ける
猫は1年に4歳、年をとります。私たち人間と同じように、猫にも年に1回以上の健康診断を受けさせることで、健康時の数値を把握し、変化を追って気付きづらい慢性腎臓病などの病気にも早期に発見できるように備えるという考え方です。
健康診断にはある程度の費用がかかりますが、さまざまな病気を早期に発見し、早期に治療を開始することで、トータルの医療費や猫への負担が軽減できることがあります。7歳を過ぎたあたりから、可能であれば年に2回以上の健康診断を受けさせられるのが理想です。
まだ若くて健康な間は、必要最小限の検査項目だけでも十分です。ある程度の年齢になったり健康状態に変化が見られた場合は、獣医師と相談しながら、必要に応じて少しずつ検査項目を増やしていきましょう。
特に腎臓病の場合、院内で実施可能な血液検査だけではなかなか早期に異常を検出できません。尿検査や超音波検査を追加することで、尿の状態や腎臓の状態をより直接的に確認することが推奨されます。また、最近では腎臓の異常をより早期に検出するための検査も利用可能になっていますので、獣医師と相談のうえで健康診断の項目に追加することも検討しましょう。
飲水量や排尿量、排尿回数などを記録する
定期的な健康診断に加えて、常日頃の飼い主様による健康状態のチェックも大切です。特に飲水量、排尿量、そしてできれば排尿回数について、記録を残し、多飲多尿などの傾向が現れたら、速やかにかかりつけの動物病院で診てもらいましょう。
猫が1日に必要とする飲水量や、適切な排尿量を求めるための計算式等もありますが、これらは食事からの水分摂取量や体内で産生される水分量など、状況によっても変わってきます。標準値との比較に過敏になりすぎるよりも、「変化に気付く」ことに重きを置くことをおすすめします。健康なうちからおおよその1日の水分摂取量と排尿回数や排尿量を把握しておきましょう。
飲水量は、器に入れた時の量から残っている量を差し引いて求めましょう。器の数だけ全て計測し、記録することを忘れないようにしましょう。
排尿量は、セットする前のペットシーツと回収する際のペットシーツの重量の差分で求めましょう。固まるタイプの猫砂を使っている場合は、塊の大きさの変化で判断しましょう。また、尿の色やニオイの変化に着目することで、より異変に気付きやすくなります。
排尿回数については、正確に把握することが難しいと思いますので、可能であればで構いません。ただ、排尿時の様子の変化も膀胱炎などに気付くきっかけとなりますので、できる場合は観察してください。
最近は、猫がトイレに入った回数や排泄量を自動で記録するトイレなども販売されていますので、導入を検討してみるのも良いかもしれません。
猫の腎臓病予防についてよくある質問

最後に、猫の飼い主様からよく寄せられる、猫の腎臓病予防に関するご質問についてご紹介します。同じ疑問やお悩みを抱えておられる飼い主様は、ぜひ参考になさってください。
アレルギー物質を避ける
アレルギー反応を引き起こすアレルゲンを避けることが、最も効果の期待できる予防法になります。治療法の「生活環境の見直し」と重複しますが、症状の改善後も、継続してアレルゲンを遠ざけるような環境維持を心掛けましょう。
日常的にアレルゲンを避けるためには、下記を意識しましょう。
-
室内は常日頃からこまめに掃除機をかける
-
花粉がアレルゲンの場合、飛散ピーク時の散歩では洋服を着用させる
-
季節にかかわらず、帰宅後には愛犬の全身を拭き取る
-
必要に応じて空気清浄機を導入する
サプリを活用しても良い?
腎臓病にサプリメントを活用することは、適切な製品を選び、獣医師の指導の元であれば一般的に安全で有益なことが多いです。ただし、製品の種類や投与の時期・量は、病期や血液検査の結果により異なることがありますので、必ず獣医師と相談することが前提です。主なサプリメント成分としては以下が挙げられます。
・リン吸着剤
・オメガ3脂肪酸(EPA/DHA)
・抗酸化物質(アスタキサンチンなど)
・プロバイオティクス
・活性炭
手作りのフードの方が予防しやすい?
尿検査や尿音波検査で腎機能の低下傾向が現れたり、多飲多尿の傾向が現れた場合は、療法食による食事療法を始めるケースが多く見られます。
これまで一般的な総合栄養食を食べていた猫たちのフードを療法食に切り替える際、多くの飼い主様が苦労されることが多いです。それまで飼い主様の手作り食を食べていた猫の場合は、切り替えがさらに難しいかもしれません。
しかし、腎臓病予防のために必要なフードの栄養バランスを実現するのはとても難しく、猫の病態によっても調整が必要になることもあります。そのため、腎臓病予防のためのフードを手作りすることは、おすすめできません。
動物病院で処方された腎臓病用の療法食の中から、できるだけ猫が好んで食べてくれる食感や風味のものを選ぶことを強くおすすめします。
まとめ 猫の腎臓病は予防が大切
今回は、猫の腎臓病について、予防という観点を中心に、原因や治療の難しさ、急性腎障害を発症させないための予防策や、慢性腎臓病を発症リスクを下げるために腎臓にかかる負荷を減らすための方法など、猫の腎臓病を予防するためのポイントをご紹介してきました。
急性腎障害も慢性腎臓病も、共に愛猫の命に関わるような病気であり、特に慢性腎臓病は一度発症すると治療では完治できない病気であるため、予防することで発症リスクを下げることが大切です。
飼い主様は、ぜひ信頼できるかかりつけの動物病院を作り、愛猫がまだ若くて健康な頃から、定期的な健康診断の受診とご自宅での愛猫の健康チェックを実践してみてください。まずは、気負わずにできることから始めていきましょう。
- 監修者プロフィール
-
岩谷 直(イワタニ ナオ)
経歴:北里大学卒業。大学研修医や企業病院での院長、製薬会社の開発や学術職などを経て株式会社V and P入社
保有資格:獣医師免許