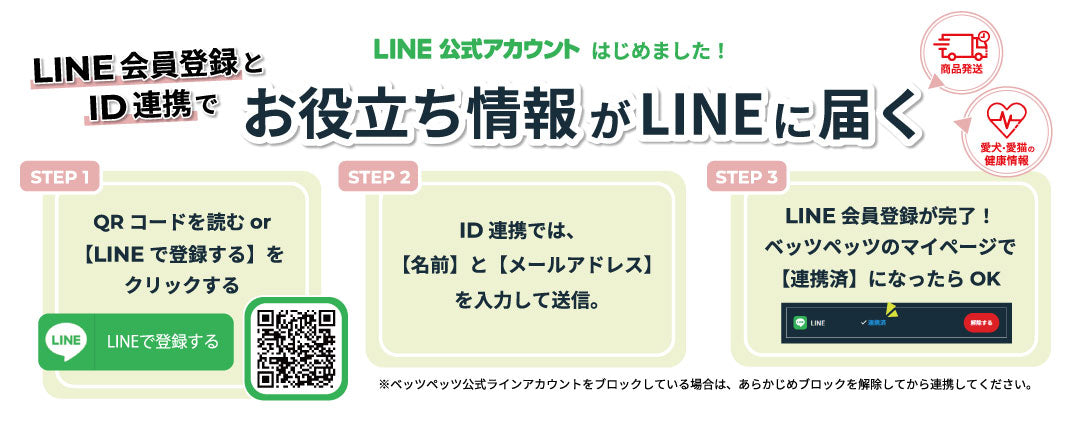【獣医師監修】犬の股関節形成不全とは?原因・症状や治療方法について解説

犬が歩きたがらなかったり、座るときに違和感があったりする様子を見て、「もしかして股関節に異常があるのでは?」と感じたことはありませんか。
犬の股関節形成不全は、成長期や遺伝的な背景によって起こることが多く、特に大型犬に多く見られる関節の病気です。進行すると痛みや歩行障害が現れるため、早期発見と適切な治療が重要です。
本記事では、股関節形成不全の基礎知識から、原因、症状、治療法、予防のポイントまで詳しく解説します。
- 目次
-
犬の股関節形成不全とは?
犬の股関節形成不全は、股関節の構造に異常があることで、関節が正常にかみ合わなくなり、痛みや歩行障害などの症状を引き起こす病気です。
股関節は、骨盤側のくぼみ(寛骨臼:かんこつきゅう)と、太ももの骨の先端(大腿骨頭:だいたいこっとう)がしっかりとはまり込むことで滑らかな動きが保たれています。しかし、この病気では骨盤側のくぼみが浅い、太もも側の骨の先端の形状が不整などの様々な理由でそのフィット感が不十分なため、関節の中で摩擦や不安定な動きが生じ、炎症や痛みにつながります。
原因は、遺伝的な要因が大きいとされていますが、急速な体重増加や過度な運動など、成長期の環境も症状の発現に影響すると考えられています。
犬の股関節形成不全の原因

股関節形成不全は、単に成長過程で起こる病気ではなく、もともとの体質と育てられた環境の両面が深く関係しています。遺伝的な傾向が強い一方で、成長期の過ごし方や飼育環境も進行や症状の重さに影響を与えると考えられています。
ここでは、発症に関与する「遺伝的要因」と「環境的要因」について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺伝的要因
犬の股関節形成不全は、遺伝的な素因を持つ犬に多く見られる疾患であり、特定の犬種では発症率が高いことがわかっています。
特にラブラドール・レトリーバーやジャーマン・シェパード、ゴールデン・レトリーバー、といった大型犬に多く見られます。
しかし、柴犬やボーダー・コリー、トイ・プードルなど、中・小型の犬種においても同様の問題が確認されており、犬種を問わず注意が必要です。
遺伝性の異常がある場合、外見上は元気に見えていても、成長とともに徐々に異常が進行し、運動の制限や痛みが現れることがあります。
環境的要因
遺伝的な要因を持っていたとしても、必ずしもすべての犬が発症するとは限りません。
カロリーの高い食事で急速に体重が増加すると、発育中の関節に過剰な負担がかかり、正常な成長を妨げる恐れがあります。また、滑りやすいフローリングの床で激しく走ったり、過度な運動を強いられたりすることで、未熟な股関節にダメージが蓄積されることも要因の1つです。
栄養、運動、住環境など、日々の小さな積み重ねが、発症や重症化に大きく関わります。
犬の股関節形成不全になりやすい犬種
股関節形成不全は、特に大型犬や超大型犬の成長期に発症しやすい病気として知られています。
成長に伴って体重が急激に増えることで、未発達の股関節に過剰な負担がかかりやすく、遺伝的な素因とあいまって関節の不安定さが目立つようになります。
一般的に骨格の成長がほぼ完了する2歳頃までは、定期的な健康チェックを通じて関節の状態を確認することが重要です。特に以下のような犬種では発症のリスクが高いとされています。
-
ゴールデン・レトリーバー
-
ラブラドール・レトリーバー
-
バーニーズ・マウンテンドッグ
-
セント・バーナード
-
ロットワイラー
-
オールド・イングリッシュ・シープドッグ
-
ジャーマン・シェパード など
日々の様子をよく観察し、歩き方や動きに違和感がある場合は早めに動物病院で診察を受けることが大切です。
犬の股関節形成不全の主な症状
犬の股関節形成不全の主な症状は下記のとおりです。
-
座るときに横座りをする
-
歩行時に腰を左右に大きく振る(モンローウォーク)
-
後ろ足を交互に動かさず、左右一緒に動かして走る(ウサギ跳びのような走り方)
-
立ち上がるのに時間がかかる、または嫌がる
-
高いところへの昇り降りを躊躇したり、避ける(ソファや階段など)
-
歩く際、後ろ足をつっぱるような不自然な歩き方をする
-
運動を嫌がるようになる、急に活動量が減る
-
立っているときに後ろ足の間隔が異常に狭い
-
後肢に力が入らず、転びそうになる
-
片足をかばうような仕草や足を浮かせて歩く
犬の股関節形成不全は、生後数ヶ月のうちから症状が現れることもあれば、成犬になってから目立ちはじめる場合もあります。
生後4〜12ヶ月の成長期に発症しやすいとされますが、2〜3歳を過ぎてから初めて異変に気づくケースも少なくありません。
また、進行の速度や症状の出方に個体差が大きく、時期によっても症状が異なります。
若い犬では、痛みが出ていても急におさまったりといった波が見られることがあります。元気に走り回っていたかと思えば急に歩きたがらなくなるなど、日によって様子が変わることがあります。
健康診断や去勢・避妊手術前のレントゲン検査などで偶然股関節形成不全が見つかることがあります。筋肉などの周囲組織による適応などにより外見上は問題がないように見えても、内部で変性が進んでいる可能性があるため、定期的な経過観察と体重管理やサプリメントなどによる早期からの関節保護への介入が重要です。
中高齢期になると、若いころからの関節の異常が徐々に進行し、痛みやこわばりが慢性化してくるケースが増えてきます。関節の変形が進んで変形性関節症へ移行すると、治療は主に進行の抑制や痛みの管理が中心です。
犬の股関節形成不全の診断方法
犬の股関節形成不全を診断する際には、外見上の違和感や歩き方の異常だけでは判断できません。
正確な診断には、飼い主からの情報提供、歩様の観察、関節の触診などの整形外科的検査、レントゲン検査などの画像診断を組み合わせる必要があります。
それぞれの検査結果を総合的に見ながら、犬の状態に合った最適な治療方針が決定されます。
犬の股関節形成不全の診断方法について詳しく見ていきましょう。
問診
動物病院で最初に行われるのが飼い主からの問診です。いつ頃からどのような様子が見られるようになったか、普段の散歩中に歩きたがらない様子はあるか、階段やジャンプを避けるようになったかといった行動面の変化について詳しく聞き取りがあります。日頃の様子についてメモをしておいたり、動画を撮っておくと役立ちます。
日常の様子を最もよく知っている飼い主から得られる情報は、動物病院にとって、初期段階の股関節形成不全の発見において極めて重要です。問診で得られた情報が、後に行う検査の方向性を決める際のヒントにもつながってきます。
歩様検査・整形外科的検査
歩き方や座り方、立ち上がる動作など、犬の自然な動きを観察することで、関節の異常を見つける手がかりが得られます。
たとえば、お尻を振るような歩き方をしていたり、横座りの癖があったり、後ろ足をそろえて走るような動作が見られる場合は、股関節に問題を抱えている可能性があります。
また、整形外科的検査では、起立姿勢や筋肉量、股関節の可動域などをチェックし、痛みの有無や骨格の左右差などを丁寧に確認します。
レントゲン検査(画像検査)
レントゲン検査は、客観的に関節の状態を確認できる検査です。
「股関節伸展位標準撮影法」によって、関節のはまり具合や骨の形状、炎症の有無などを視覚的に捉えることができます。ただし、見た目に異常がなくても緩みが隠れていることがあるため、Penn HIP(ペンヒップ)法という特殊な撮影技術を用いて、股関節の緩みを数値的に評価するケースもあります。
従来のレントゲン撮影方法では2歳にならないと精度の高い診断ができませんでしたが、Penn HIPは生後16週からの検査によって、将来的なリスクの予測や早期対応に役立ちます。ただし、より正確な診断を行うためにレントゲン撮影時に深い鎮静や全身麻酔が必要になることがあります。Penn HIP法による診断はどの病院でも出来るわけではなく、認定医の所属している病院を探す必要がありますので、病院のホームページなどで確認してみましょう。
犬の股関節形成不全の治療方法

股関節形成不全は、放置すると関節の変形が進行し、痛みや歩行障害が悪化する可能性があります。
そのため、症状の程度や犬の年齢・生活環境に応じて、内科的治療(保存療法)と外科的治療のいずれか、もしくは両方を組み合わせた治療が検討されます。
それぞれの治療法の特徴や選択のポイントについて解説します。
内科的治療(保存療法)
内科的治療では、関節の痛みや炎症を緩和し、日常生活に支障をきたさないようにすることが中心です。消炎鎮痛薬やサプリメントの使用や適正体重の維持による関節負担の軽減を行います。痛みは、活動量の減少、食欲低下、攻撃性の増加、睡眠障害など多面的な負の影響を及ぼす可能性があるため、痛みの管理は特に重要となります。
また、筋力を維持するための軽い運動療法や、水中歩行などのリハビリも取り入れられることがあります。ただし、あくまでも進行の抑制や症状の緩和が目的であり、骨の変形そのものを元に戻すことはできません。
進行した股関節形成不全に対する効果に限界がある点も理解しておく必要があります。
外科的治療
内科的なアプローチで効果が見られない場合や、犬のQOL(生活の質)を著しく損なうような症状が出ている場合には、外科的治療が検討されます。
外科手術には「若齢犬恥骨結合癒合法(JPS)」「大腿骨頭・骨頚切除術(FHO)」「三点骨盤骨切術(TPO)」「股関節全置換術(THR)」などがあります。
どの手術を行うかは、犬の年齢や体格、症状の進行度、術後のケア体制などを総合的に考慮したうえで決定されます。手術には麻酔や術後管理のリスクも伴うため、飼い主と獣医師がしっかりと話し合い、納得のいく選択をすることが大切です。
犬の股関節形成不全の予防
股関節形成不全には遺伝的な要因が深く関与しているため、すべての発症を防ぐことは困難です。しかし、日々の生活習慣や環境を整えることで、発症のリスクを抑えたり、症状の進行を緩やかにできる可能性はあります。
ここでは、股関節形成不全の予防のために意識したいポイントを詳しく紹介します。
適切な食事や運動による健康維持
成長期の子犬は骨や関節が急速に発達する時期であり、栄養バランスの整った食事と無理のない運動が特に重要です。過剰な食事やおやつによる急激な成長や過体重は、未成熟な股関節に大きな負担をかけ、形成不全を引き起こすリスクが高まります。これまでの研究でも成長期に適正体重を維持することが股関節形成不全の発生を有意に低下させることが報告されています。
そのため、食事量の管理はもちろん、与えるフードの栄養成分にも配慮することが求められます。
また、散歩などの軽度な運動は、関節周囲の筋肉を育て、股関節の安定に役立ちます。ただし、高い場所からのジャンプや急なダッシュといった激しい運動は関節にダメージを与える可能性があるため、日々の運動内容には注意が必要です。
必要に応じて動物病院で相談し、関節をサポートするサプリメントを取り入れるのも方法の1つです。
生活環境の改善
股関節への負担を軽減するためには、犬が生活する環境そのものを見直すことも重要です。滑りやすいフローリングの床や急な段差は、足を滑らせたり、着地の衝撃で関節を痛める原因となることがあります。
マットやカーペットを敷く、ソファやベッドに上がる際にステップを用意するなど、足腰に優しい環境づくりを心がけましょう。
また、足裏の毛が伸びすぎると滑りやすくなり、爪が伸びすぎると踏ん張りが利かず、関節への負荷につながります。足裏の毛カットや爪切りを習慣づけることで、ケガのリスクや股関節への負担を軽減できます。
成長期の検査による早期発見
股関節形成不全は、成犬になってから認識できる症状が現れることもありますが、実際には成長期の骨格形成時から進行していることもあり、更に犬は本能的に痛みを隠そうとすることがあるため飼い主が症状に気づきにくいことが少なくありません。特にリスクの高い犬種の場合は、レントゲン検査を受けておくことが、早期発見・早期対策につながります。
骨格が完成に近づく1歳〜2歳頃までに一度検査を行っておくと、股関節のゆるみや異常にいち早く気づくことができます。
さらに、定期的な健康診断を受けることで、体重の増減や運動量の変化など、日常では見過ごしがちなサインにも早めに対応できるようになるでしょう。
まとめ 犬の股関節形成不全は早期の治療が大切
犬の股関節形成不全は、進行性の疾患である一方、日々の生活習慣や早期対応によって症状を軽減・コントロールできる可能性があります。
成長期における体重管理や生活環境の見直し、定期的な健康診断の受診が予防と早期発見において重要です。
歩き方に違和感があったり、運動を嫌がるような様子が見られたら、早めに獣医師に相談しましょう。
- 監修者プロフィール
-
岩谷 直(イワタニ ナオ)
経歴:北里大学卒業。大学研修医や企業病院での院長、製薬会社の開発や学術職などを経て株式会社V and P入社
保有資格:獣医師免許