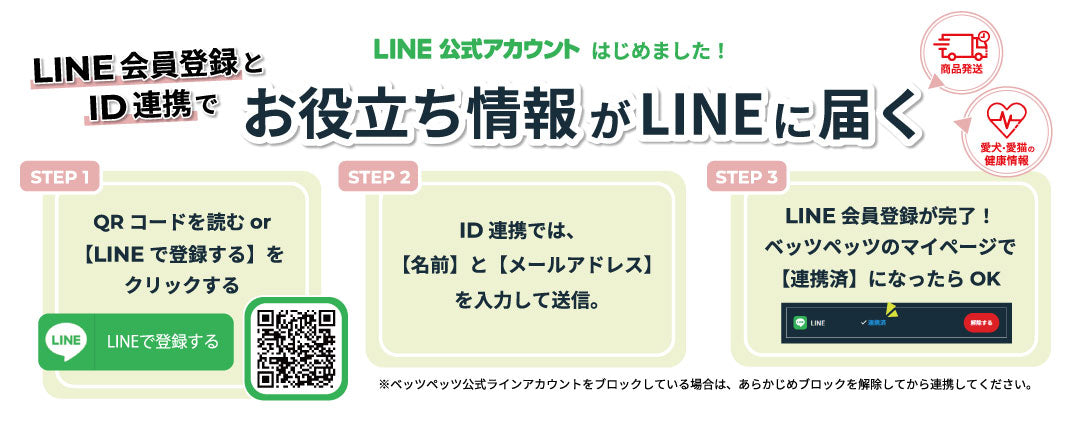【獣医師監修】犬のごはんの量はどう決める?計算方法や目安について

「うちの子にちょうどいい食事量がわからない」「フードの量を計算する方法を知りたい」と悩む飼い主さんも多いのではないでしょうか。犬に適したごはんの量は、犬種や体重だけでなく、年齢や健康状態、運動量などによっても異なります。
本記事では、体重別のごはんの目安や、カロリー計算による適切なフード量の求め方を詳しく解説します。
- 目次
-
-
【体重別】犬のごはん量の目安
・小型犬(10kg未満)の場合
・中型犬(10~25kg)の場合
・大型犬(25kg以上)の場合 -
犬のごはん量の計算方法
・手順1:1日のエネルギー要求量を計算
・手順2:適切なごはんの量を計算
- 犬のごはんの回数・タイミング
-
犬のごはん量を決める時の注意点
・年齢や健康状態なども考慮する
・量だけではなく質も大切 -
犬のごはん量についてよくある質問
・犬が肥満気味・痩せ気味な時のごはん量は?
・犬のごはんが足りていないサインは?
・犬にドッグフード以外のごはんを与えてもいい?犬にドッグフード以外のごはんを与えてもいい?
・おやつを与える場合はごはんの量を減らす? - まとめ 犬のごはんの量がわからない時は獣医師に相談する
-
【体重別】犬のごはん量の目安
【体重別】犬のごはん量の目安
犬に与えるごはんの量は、犬種や年齢、健康状態、運動量によって異なります。
ここで紹介するのは、一般的な成犬の適正体重における目安量であり、あくまで一例です。各犬種の目安量は調べることで確認できますが、年齢や健康状態を踏まえた適切なごはんの量がわからない場合は、獣医師に相談すると安心です。より理想的なごはんの量を知るための計算方法も本記事で紹介していますので、そちらも参考にしてみてください。また、ごはんの量の調整に関わる脂肪の付き具合などの体型に関して、家庭でも常にBCS(ボディコンディションスコア)に準じたチェックで、痩せていないか、あるいは太っていないかの確認も行うようにしましょう(BCSに関してはの記事もご参照ください:「犬の肥満」記事への内部リンクを設置)。
愛犬の体調やライフスタイルに合わせて調整しながら、適切な食事管理を心がけましょう。
小型犬(10kg未満)の場合
小型犬に適したごはんの量は、体重に加えて、犬種やご飯の種類によって幅があります。与えているフードのラベルに体重別の量が必ず記載されていますので、理想体重にあてはまる量を与えてください。あくまで一例ですが、犬種別の1日のごはんの量は、下記が目安です(ドライフード)。
(例)
-
トイプードル……70~120g程度
-
ポメラニアン……45~50g程度
-
キャバリア……100~145g程度
ごはんの量は、活動量や体質などに応じて調整が必要です。毎日の食事の様子や体重の変化を観察しながら、適切な量を見極めていきましょう。
中型犬(10~25kg)の場合
中型犬のごはんの量は小型犬と比べて多く、犬種によって適量が異なります。小型犬同様、与えているフードのラベルを確認して、理想体重にあてはまる量を与えてください。
こちらもあくまで一例ですが、中型犬における犬種別の1日のごはん目安量は、下記の通りです(ドライフード)。
(例)
-
柴犬……128~183g程度
-
ビーグル……170g程度
中型犬は個体差が大きく、運動量や体質によって適切なごはんの量が変わります。定期的に体重を測定し、愛犬の体調を考慮しながら調整していきましょう。
大型犬(25kg以上)の場合
大型犬のごはんの量は中型犬よりも多く、犬種によって適量が異なります。
小型犬と異なり、体重幅が大きくなっていますので、与えているフードのラベルを必ず確認しながら、理想体重にあてはまる給与量を与えてください。
犬種別の1日のごはんの量としては、例えば下記の目安があります。
(例)
-
ゴールデンレトリーバー……750g前後
-
シベリアンハスキー……600g前後
定期的な体重測定と健康チェックを行いながら、バランスの取れた食事管理を心がけてください。
犬のごはん量の計算方法

体重や年齢、活動レベルに応じて必要なカロリーは異なるため、愛犬に合った適切な量を知ることが大切です。適切なごはんの量を確認するには、1日のエネルギー要求量を把握し、その後、犬に適したごはんの量を計算します。
ここでは、犬のごはん量の計算方法について詳しく解説します。
手順1:1日のエネルギー要求量を計算
まずは、愛犬が1日に必要とするエネルギー量(摂取カロリー)を求めましょう。犬のごはんの量は「安静時エネルギー要求量(RER)」と「1日のエネルギー要求量(DER)」という2つの数値をもとに算出します。
安静時エネルギー要求量(RER)は、犬が安静に過ごしている状態で必要とするカロリーを指し、この数値に活動係数をかけることで1日のエネルギー要求量(DER)を求められます。
計算の方法は、①簡易的に算出できる方法、②①より正確なごはんの量を算出する2通りがあります。②の計算では√(ルート)の機能が使用できる計算機(携帯電話の電卓でも可能です)が必要になります。
それぞれの方法による安静時エネルギー要求量の計算方法は、下記のとおりです。
① 簡易的な方法での安静時のエネルギー要求量(RER)の算出方法
「体重(kg)×30+70」で算出
② より正確な安静時のエネルギー要求量(RER)の算出方法
-
体重(kg)の3乗を求める
-
その値の平方根(√)を2回押す
(電卓の場合。携帯電話のアプリを使用する場合は使用方法が異なります。また、機種によっても使用方法が異なることがあります。)
-
得られた数値に70をかける
例:体重8kgの場合のRER
1……8×8×8=512
2……512√√=4.7568
3……4.7568×70=332.976(約330kcal)
例:体重3.5kgの場合のRER
1……3.5×3.5×3.5=42.875
2……42.875√√=2.559
3……2.559×70=179.13(約180kcal)
1日のエネルギー要求量は、安静時エネルギー要求量に犬の成長段階や活動レベルに応じた「活動係数」をかける「RER×活動係数」で求められます。
活動係数は下記のとおりです。
|
犬の成長段階・状態 |
活動係数 |
|
生後3カ月まで |
3.0 |
|
生後4〜9ヶ月 |
2.5 |
|
生後10〜12ヶ月 |
2.0 |
|
成犬(避妊、去勢なし) |
1.8 |
|
成犬(避妊、去勢済み) |
1.6 |
|
肥満気味の成犬 |
1.4 |
|
減量中の成犬 |
1.0 |
|
シニア犬(避妊、去勢なし) |
1.4 |
|
シニア犬(避妊、去勢済み) |
1.2 |
例:体重8kgの成犬(肥満気味の成犬)
332.976×1.4=466.1664(約466kcal)
例:体重3.5kgの成犬(避妊、去勢済み)
179.13×1.6=286.608(約287kcal)
進行すると、細菌の二次感染によって症状が悪化することもあるため、注意が必要です。
手順2:適切なごはんの量を計算
手順1で求めたエネルギー要求量をもとに、適切なごはんの量を計算します。
計算にはドッグフードのカロリーを使用しますが、食べているドッグフードによってカロリーの含有量が異なるため、事前にパッケージなどでカロリーを確認しましょう。
1日のドッグフードの適切な量は下記のように計算します。
(手順1で求めた)1日のエネルギー要求量÷ドッグフードの100gあたりのカロリー×100
例:体重8kgの成犬(肥満気味の成犬)、ドッグフード250kcal/100g
466÷250×100=約186g
例:体重3.5kgの成犬(避妊、去勢済み)、ドッグフード300kcal/100g
287÷300×100=約96g
犬のごはんの回数・タイミング
犬のごはんの回数やタイミングは、年齢や健康状態、運動量によって適切な頻度が異なります。一般的には成犬の場合、1日2回の食事が基本となりますが、幼年期や老犬(シニア)期では、それぞれのライフステージに応じた配慮が必要です。
生後1年未満の幼年期は、消化器官が未発達で一度に多くの食事を消化することが難しいため、回数を増やして小分けに与えることが推奨されます。
生後2ヶ月頃までは1日4回、生後4ヶ月頃から3回に減らし、生後6ヶ月以降は徐々に1日2回へと移行していきます。
成犬期では、食事の回数は1日2回が目安です。朝と夕に均等な時間を空けて与えることで、犬の体内時計が整い、健康的な生活習慣を維持しやすくなります。
老犬(シニア)期になると、食欲が減少したり、消化機能が衰えることがあります。小型・中型犬では7〜8歳、大型犬では5〜6歳頃からが目安とされており、食事の回数を増やすことで、1回のご飯量を減らして消化しやすくすることが1つの方法です。
ごはんを与えるタイミングや適切な時間については、別記事で詳しく解説しておりますのでぜひ参考にしてください。
- こちらの記事もご参考してください
-
犬のごはんにベストな時間は何時?獣医師が朝・昼・夜の最適なタイミングと健康管理を解説:
https://vetzpetz.jp/blogs/column/dog-food-time
犬のごはん量を決める時の注意点

犬のごはんの量を決める際には、単に体重や犬種だけで判断するのではなく、さまざまな要素を考慮することが重要です。愛犬にとって適切な食事量なのかを確認する上でもっとも重要なことは体重の増減を確認することです。人でも太りやすい人、やせやすい人がいます。犬も同様に個体差がありますので、体重測定を定期的に行って、体重の増減を確認しながら、ご飯の量を調整していきましょう。犬のごはんの量を決める際の注意点について、詳しく見ていきましょう。
年齢や健康状態なども考慮する
犬のごはんの適量は、年齢や健康状態、運動量などによって大きく変わります。同じ体重の犬であっても、成長期の子犬とシニア犬では必要なエネルギー量が異なります。
そのため、一律に決められた分量を与えるのではなく、愛犬の状態に合わせて適切な量を調整することが重要です。
特に成長段階にある子犬はエネルギー消費が激しく、頻繁に食事を摂る必要があります。
成犬になると、基本的には朝と夜の2回に分けて食事を与えるのが適切ですが、運動量や体質によっては適量が異なります。
愛犬の適切なごはん量がわからない場合や、食欲の変化が気になる場合は、獣医師に相談するのが安心です。
量だけではなく質も大切
犬の健康を維持するためには、食事の量だけでなく、質にも十分な注意を払うことが大切です。
ペットフードの栄養基準を決めている世界的な団体として、AAFCO(The association of American Feed Control Officials)があり、犬における成長期及び維持期(成犬期以降)に必要な栄養素の最低値を設定しています。日本で販売されている総合栄養食と書かれたペットフードの殆どは、このAAFCOの栄養基準値を元に作られています。
AAFCOの基準によると、犬では炭水化物は必須の栄養素ではないため、基準が設定されていません。とはいえ、脳の活動には糖質が必要ですし、糖分がないとエネルギー源として体の構成成分であるタンパク質が消費されてしまい、生理機能の維持に影響が及ぶ可能性があるため適量の炭水化物の摂取は必要になります。一般的なペットフードには30~60%炭水化物が含まれているようです。維持期におけるタンパク質と脂質の基準値はそれぞれ18%、5.5%となっています。ビタミンやミネラル等の他の栄養素にも基準値が設定されていますので、ドッグフードを選ぶ際は成分表を確認し、AAFCOの基準値をクリアしている栄養バランスが適切なものを選びましょう。
手作りごはんを与える場合は、栄養の偏りに特に注意が必要です。
同じ食材ばかりを与えてしまうと、栄養が偏る原因になります。
さらに、手作り食を続ける場合、ミネラルの不足にも注意が必要です。特に鉄分やカルシウム、亜鉛が不足しがちで、長期間にわたって不足すると貧血や骨、皮膚の健康に問題を引き起こす可能性があります。ただし、不足しがちだから多めに与えればいいかというと、そういうわけではありません。ミネラルは互いの量に相互関係があり、一方が過剰になると他のミネラルが不足してしまうという現象が起こってしまいます。AAFCOでは過剰摂取により影響が生じる可能性がある栄養素に関しては上限値を設定していますので、こちらも確認してみてください。
自己流での食事管理は栄養不足を招くリスクがあるため、獣医師に相談して適切なメニューを組むのが安心です。
犬のごはん量についてよくある質問

犬のごはんの量については、多くの飼い主が疑問を持っています。そこで、犬のごはんの量について、よくある質問に回答します。
犬が肥満気味・痩せ気味な時のごはん量は?
肥満は寿命の短縮や糖尿病、高血圧、関節炎、呼吸器系の病気のリスクを高める要因です。また、肥満は体内での慢性的な炎症状態を引き起こすと言われています。慢性炎症はがんを引き起こす要因の1つとも言われます。愛犬の健康管理のために、体重管理は非常に重要なことです。
体が重くなることで運動能力が低下し、散歩や遊びを楽しめなくなったり、階段の上り下りが困難になったりすることもあり、QOLの低下も引き起こしてしまいます。
一方で、痩せ気味の犬の場合、栄養不足による免疫力の低下や筋肉量の減少が懸念されます。
肥満や痩せの状態を改善するには、ごはんの量だけでなく、食事の質も見直す必要があるでしょう。
カロリーが高すぎるドッグフードを与えている場合は低カロリーのものに切り替える、栄養価の高いフードを選んで必要なエネルギーを補うなど、食事の調整を行うとよいです。
健康的な体重を維持するためには、犬のサイズや年齢、運動量に応じた適切な食事管理が大切です。
自己判断で大幅に食事量を変えてしまうと、かえって健康を損なう可能性があるため、体型の変化が気になる場合は獣医師に相談することをおすすめします。
犬のごはんが足りていないサインは?
ごはんの量が適切かどうかを判断するためには、体重の変化や便の状態を観察することが重要です。
定期的に体重を測定し、適正な範囲で推移しているかを確認しましょう。
病気の徴候がないのに体重が減り続けている場合は、エネルギーが不足している可能性があります。反対に、病気の徴候がないのに体重が増え続けている場合は、必要以上のカロリーを摂取している可能性があるため、食事の見直しが必要です。
また、便の状態もごはんの適量を判断するポイントになることがあります。理想的な便は、ティッシュなどでつまみ上げた時に、トイレシートに少し跡が残る程度の軟らかさがあります。
便が軟らかすぎる場合は、ごはんを与えすぎていることで消化が不十分になっている可能性があるため、少し減らすなどで様子を見てみましょう。
ただし、便の状態は、水分や体調などによっても左右されます。必ずしも食事に原因があるとは限らないため、愛犬をよく観察し、長期間にわたって便の状態が悪い時は、獣医師に相談してください。
犬にドッグフード以外のごはんを与えてもいい?
犬にドッグフード以外の手作りごはんを与えることは可能ですが、栄養バランスや食材選びには注意が必要です。
動物性タンパク質を中心に、野菜や炭水化物をバランスよく取り入れましょう。
肉類や魚、にんじん、小松菜、えのき、ご飯などが適していますが、ネギ類、カカオ、アボカド、ブドウ、生の甲殻類など、健康に悪影響を及ぼすため、与えてはいけない食材も多くあります。
頻繁に手作りごはんを取り入れる際は、栄養の偏りや避けるべき食材を与えてしまうことを防ぐため、獣医師に相談することが望ましいです。
おやつを与える場合はごはんの量を減らす?
おやつを与える際には、カロリーを考慮しなければなりません。
ドッグフードで必要な栄養をしっかり摂取できている場合、おやつの与えすぎは肥満の原因になる可能性があります。また、おやつの多くは嗜好性を重視しているため、主食のドッグフードを食べなくなったり、おやつの食べ過ぎで主食の食欲が減退し、栄養バランスが崩れる可能性もあります。
そのため、おやつのカロリーを含めても、1日の摂取カロリーは超えないように管理することが重要です。
一般的な目安として、おやつのカロリーは1日の摂取カロリーの1割~2割程度に抑えましょう。たとえば、1日の摂取カロリー量が500kcalの犬であれば、おやつは50~100kcal以内が目安となります。おやつを与えるのであれば、その分の主食のカロリーは400~450kcalに抑えます。
まとめ 犬のごはんの量がわからない時は獣医師に相談する
適切なごはんの量を知ることは、愛犬の健康維持のために欠かせません。
本記事では、体重別の目安や計算方法、与える回数やタイミングについて詳しく解説しましたが、年齢や健康状態、運動量などによって最適な量は異なるため、注意が必要です。
愛犬が食事をする様子を観察しながら、適切な食事管理を行うことが大切です。特に、体重の変化や便の状態を定期的にチェックすることで、ごはんの量が足りているかどうかを判断しやすくなるでしょう。
食事の量や内容を変える場合も、急に変えるのではなく、徐々に変えていきながら観察するのが基本です。自己判断だけで食事量を大きく変更するのはリスクを伴うため、不安を感じたら獣医師に相談することが大切です。
- 監修者プロフィール
-
岩谷 直(イワタニ ナオ)
経歴:北里大学卒業。大学研修医や企業病院での院長、製薬会社の開発や学術職などを経て株式会社V and P入社
保有資格:獣医師免許