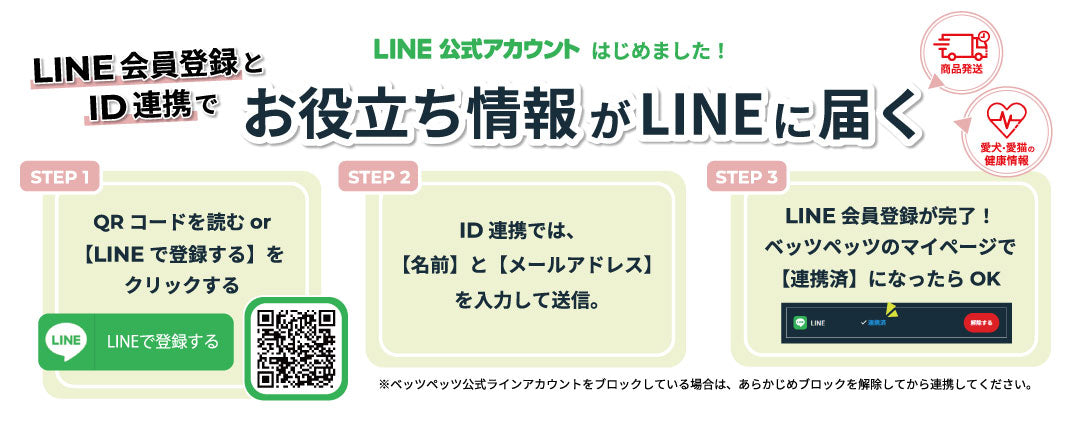犬のフケは皮膚病を疑うべき? 皮膚病の原因と改善方法とは

犬のフケに悩んでいる飼い主の方も多いのではないでしょうか。フケは乾燥やシャンプーなどの外的要因によるものもあれば、皮膚病が原因で現れる場合もあります。本記事では、犬のフケが出る原因や考えられる皮膚病、改善方法などについて解説します。
- 目次
犬のフケが出る原因とは?皮膚病を疑うべきか

フケは、古い角質が剥がれたもののため、必ずしも皮膚病の症状とは限りません。犬のフケが出る原因について詳しく見ていきましょう。
乾燥
犬の皮膚は、表面に角質細胞と呼ばれる細胞がレンガの壁を形成するように並んでいます。この角質細胞がたくさん積み重なるといわゆる角質層が作られ、新陳代謝にともなって古くなった角質細胞が脱落し新しい皮膚と入れ替わります。フケはその際に脱落したもので、一定のサイクルで発生します。この、皮膚の細胞が古いものから新しいものに入れ替わる流れをターンオーバーと言います。健康な犬の場合は、皮膚のターンオーバーは約3週間と言われています。
角質細胞と角質細胞の間は脂分が埋めており、また角質の表面も皮脂で覆われ、角質が脱落しにくくなっています。乾燥すると角質細胞の間の脂分や皮脂が少なくなり、角質細胞が過度に剥がれやすくなるため、フケが目立つようになります。特に、冬の乾燥した季節やエアコンの使用によって乾燥が進むと皮膚が乾いて剥がれ落ちやすくなり、フケの量が多くなることがあります。
皮膚病
ノミやダニなどのアレルギー性皮膚炎によって、赤みやかゆみとともにフケが増えることがあります。また、アトピー性皮膚炎の犬もフケが出やすくなります。
花粉やハウスダストなどが原因でアレルギー反応を引き起こしやすい犬は、皮膚が赤くなる症状が見られることがあります。アレルギーは耳や口、目の周り、足先の指の間、足の内側、おなかなどに皮膚症状がみられる事があるため、これらの部位に赤みが出ていないか日常的に確認してみましょう。
他にも、細菌性の皮膚炎や脂漏症も考えられます。脂漏症は、ベタついた状態になる脂性脂漏症とフケが増える乾性脂漏症とがあります。脂漏症のように皮脂が過剰になると犬ではターンオーバーが通常の3週間から1週間に短縮するとの報告もあるようです。
外的要因
シャンプーの刺激が愛犬の皮膚には強過ぎてフケが増えることもあります。シャンプーの回数が多かったり、シャンプーの成分が愛犬の皮膚に合わなかったりすると、ダメージを受け一時的にフケが増えてしまうことにもつながります。また、トリミングで毛を短く刈ると、一時的にターンオーバーが早くなることがあります。犬の毛も皮膚のバリアとして重要な役割を担っているため、毛が短くなることで補助的に角質が多く産生されると考えられています。
ストレス
犬が日常生活でストレスを感じていると、交感神経の働きが活性化し、毛が逆立ちやすくなります。毛が逆立つと古くなった皮膚の角質も浮き上がるため、結果としてフケが増えることがあります。犬が頻繁にあくびをしたり、体をブルブル振る、唸る、吠えるなどの行動は、ストレスを感じているサインである可能性があります。日頃から、愛犬の生活環境や行動先でストレスを抱える状況がないか確認してみてください。
犬のフケの原因となる皮膚病

フケが出たからといって必ずしも皮膚病が原因とは限りませんが、早期に治療を始められるように症状を確認しておくことが大切です。犬のフケを引き起こす皮膚病の種類とそれぞれの特徴や症状について、詳しく見ていきましょう。
感染性皮膚炎
感染性皮膚炎は、細菌や真菌などの感染によって引き起こされる皮膚炎です。主な感染性皮膚炎の種類とそれぞれの症状、原因は下記のとおりです。
|
名称 |
症状 |
原因 |
|
マラセチア |
ベタベタと脂っぽくなり、赤みやかゆみ、フケ、色素沈着、苔癬化(皮膚が厚くなり、表面のしわや溝が深くなった状態)が生じる。 わきの下やあご、お腹、足の指の間、肛門周りなどに現れる。 |
酵母様真菌「マラセチア」の感染が原因。 マラセチアは皮脂を分解する菌としてもともと皮膚に少数存在するものの、増えすぎることで皮膚症状を引き起こす。 |
|
膿皮症 |
フケ、赤み、発疹、かゆみ、脱毛、色素沈着、においが生じる。 |
主に「ブドウ球菌」の感染が原因。 ブドウ球菌はもともと皮膚に存在するものの、抵抗力の低下や他の皮膚病などの影響で異常増殖して症状を引き起こす。 病変の深さにより、表面性膿皮症、表在性膿皮症、と深在性膿皮症(真皮深く)に分類される。 |
|
皮膚糸状菌症 |
赤みやフケの増加に続き、進行するに従いかさぶたをともなう円形の脱毛が生じる。 頭部や耳、前肢、尻尾などに見られることが多い。 |
真菌の一種「皮膚糸状菌」の感染が原因。 皮膚の角質層や爪、被毛などに侵入・増殖して症状を引き起こす。 |
アレルギー性皮膚炎
アレルギー性皮膚炎は、アレルゲンが原因で皮膚に赤みやかゆみ、フケなどを引き起こす病気です。症状が現れやすい部位は耳、脇、股、足先、口や目の周りなどです。
アレルギー性皮膚炎は、原因物質であるアレルゲンの種類により下記の4つに分類されます。
|
分類 |
特徴 |
|
アトピー性皮膚炎 |
ハウスダストや花粉、カビなどの環境中のアレルゲンが体内に侵入することで発症する。 |
|
食物アレルギー |
食べ物に含まれる特定の成分に対してアレルギー反応を起こすことで発症する。皮膚症状に加えて外耳炎や下痢などが現れることがある。 |
|
ノミアレルギー |
ノミの唾液中のタンパク質がアレルゲンとなり、吸血時に体内へ取り込まれることで起こる。 |
|
接触性アレルギー |
食器やカーペットなど皮膚に触れるものがアレルゲンとなり、症状が現れる。 |
進行すると、細菌の二次感染によって症状が悪化することもあるため、注意が必要です。
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎とは、皮膚のかゆみをともなう慢性のアレルギー性皮膚炎であり、主にハウスダストマイト(室内のダニ)や花粉などの環境アレルゲンに対して過敏に反応します。
「アトピー体質」と呼ばれるアレルギー反応を起こしやすい遺伝的な要因が関係しており、若い頃(特に1歳~3歳頃)に発症することが多いです。症状は年齢とともに進行し、治療をしないとかゆみが増す傾向にあります。
アトピー性皮膚炎の犬は、皮膚のバリア機能が弱いため乾燥しやすく、外部からの刺激に敏感です。かゆみだけではなく、赤みやフケなど、さまざまな症状が現れます。
症状が現れやすい部位は、足先、脇、足の付け根(内股)、目や口の周りなどです。頻繁にかくことによって掻き壊しによる出血などがみられる事があり、慢性化すると皮膚が厚くなったり、色素沈着によって黒ずんだりすることもあります。
脂漏症
脂漏症は、「脂が漏れる」と書きますので、一般的には皮脂が過剰になることによる皮膚のトラブルと認識されますが、皮脂の量が過剰になるだけではなく、皮脂に含まれる成分のバランスが異常になっていることで皮膚にトラブルを引き起こす場合もあります。皮脂の量や成分バランスが崩れると、表皮のターンオーバーに異常が生じ、フケが多くなります。皮脂の量が多くなり皮膚のベタツキとフケを伴った状態を油性脂漏症、ベタツキはないがフケが多い状態は乾性脂漏症と呼ばれます。
脂漏症の発症は、下記のような要因が原因と考えられています。
-
遺伝的に脂腺の数が多い、ターンオーバーが正常に行われないなど、脂漏症になりやすい体質を持っている
-
皮膚炎や甲状腺ホルモンなどの代謝に関連したホルモンのバランス異常、栄養管理の不良、誤ったスキンケアなどによってターンオーバーに異常をきたす
脂っぽい肌とフケが出る肌が混在することもあり、特に背中の部分は脂腺の数が多いためフケが出やすくなる傾向にあります。
甲状腺機能低下症
甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンの分泌が低下することで全身の代謝が低下し、さまざまな症状を引き起こす病気です。甲状腺は喉仏(のどぼとけ)の下にある内分泌器官で、体の代謝を活性化するホルモンを分泌しています。
主な症状は下記のとおりです。
皮膚・被毛の異常(もっとも一般的)
· 被毛が薄くなる、脱毛(特に尾や胴体)、毛がパサつく
· 皮膚が黒ずむ(色素沈着)、フケが増える
· 皮膚の感染症(マラセチアや細菌によるもの)が起こりやすくなる
代謝の低下
· 体重の増加(食事量が変わらなくても増加する)
· 活動性の低下、疲れやすい、寝ていることが増える(嗜眠傾向)
· 寒がる
神経症状
· 後ろ足のふらつき、運動失調
· 顔面神経麻痺(稀)、ぼんやりする、認知機能低下等
その他
· 心拍数の低下
甲状腺機能低下症の原因としては、免疫介在性疾患や遺伝的な要因、甲状腺に悪影響を与えるそのほかの疾患などが挙げられます。
最も一般的な原因は免疫介在性疾患であり、自身の免疫システムが甲状腺を誤って攻撃し、破壊してしまうことで、甲状腺ホルモンの分泌が減少します。
そのほかの原因としては、腫瘍や副腎皮質機能亢進症などもあります。
犬のフケを改善する方法

犬のフケを改善するためには、原因を特定して適切な対策をとることが大切です。フケは乾燥や皮膚炎、アレルギーなど様々な原因で発生することが多いため、以下の方法で改善を試みることもできます。
皮膚疾患の確認と適切な治療を受ける
フケが出るだけでなく、赤みや脱毛、痒みなどの皮膚に関連した症状が見られる場合は皮膚疾患やアレルギーなどの可能性も考えられるため動物病院を受診し、疾患が存在していないかチェックしてもらいましょう。疾患が見つかった場合は獣医師の指示に従い適切な治療を受けましょう。
皮膚の健康を支える栄養素が強化された食事をとる
基本的には、総合栄養食と記載されているドッグフードの摂取で、皮膚の健康を維持するのに必要な栄養素は摂取出来ますが、皮膚の健康を支えるために必須脂肪酸などの栄養素が強化された食事を与えてもいいかもしれません。また、食事を変更する代わりに、栄養素をサプリメントで補充することも可能です。食事の変更やサプリメントの給与を検討する際は、獣医師に相談しましょう。
シャンプーとスキンケアを見直す
シャンプーが原因でフケが過剰になっていると考えられる場合は、シャンプーの種類や頻度を見直してみましょう。ヒトの皮膚pHは弱酸性ですが、犬は中性から弱アルカリ性と言われています。皮膚に刺激の少ないシャンプーを獣医師と相談しながら探してみましょう。シャンプーの頻度は、皮膚のターンオーバーが3週間であることから一般的には月に1~2回程度が理想とされています。その他、保湿用のスプレーなどを組み合わせて使用することで皮膚の状態を健康に維持できることがあります。
適度なブラッシング
適度なブラッシングは、毛玉防止、衛生面のケアなどにより皮膚のトラブルを防ぐことができ、結果としてフケを予防、改善できることがあります。短毛種であれば2~3日に1回、長毛種であれば1日1回、1回に5分程度を目安に行ってください。過剰なブラッシングや全身的な皮膚病があるときのブラッシングは、皮膚にダメージを与える可能性があるので控えましょう。また、犬用のブラシには、皮膚にダメージを与えにくいようブラシのピン先がキューブになったタイプや、抜け毛を除去しやすいスリッカーブラシなど、いくつかの種類があります。皮膚にダメージの少ないブラシに変えることで、フケが出にくくなることもあります。
ストレス改善を試みる
愛犬がストレスを感じている環境を変えることがフケ改善につながることも稀にあります。たとえば、留守番している時間の長さや室内環境の見直しなど。犬のストレス症状はフケの他に下痢や嘔吐など胃腸に現れることもあります。ストレスになる環境や状況がないかをチェックし、原因を取り除けるよう改善していきましょう。
まとめ 皮膚病が疑われる場合は動物病院へ
犬のフケの原因は、乾燥のような外的要因によるものから、感染性皮膚炎やアレルギー性皮膚炎など病気によるものまでさまざまです。
赤みや脱毛、かゆみ、臭いといった他の症状がともなう場合は、皮膚病の可能性が高いと言えます。フケやそのほかの症状が気になる場合は、早めに動物病院を受診しましょう。
犬の血尿がみられる場合は、獣医師がより正確に診断できるよう、排尿回数や排尿量、色調や犬の様子などを伝えてください。犬の健康を守るためにも、普段から様子を細かく確認し、万が一の際には速やかに行動できるようにしましょう。
- 監修者プロフィール
-
岩谷 直(イワタニ ナオ)
経歴:北里大学卒業。大学研修医や企業病院での院長、製薬会社の開発や学術職などを経て株式会社V and P入社
保有資格:獣医師免許