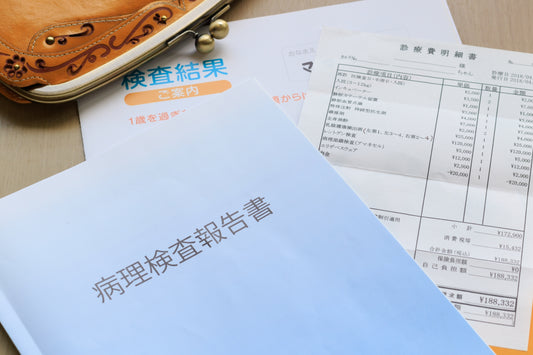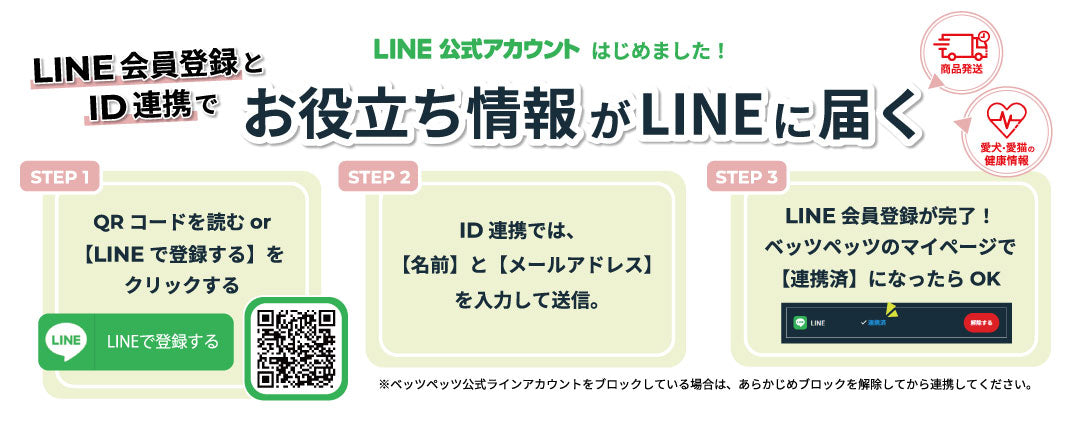【獣医師監修】腎臓病の犬が食事で取り入れるべき栄養は?食べてはいけないものも紹介

腎臓病の犬の食事に関して「どの栄養素を摂るべきか?」「食べてはいけないものは?」と悩んでいませんか?
腎臓病の犬には、腎臓への負担を軽減するための食事管理が必要です。たんぱく質やリンの制限、オメガ3系脂肪酸の摂取など、腎臓を守るためのポイントを押さえることで、愛犬の健康維持に役立ちます。
本記事では、腎臓病の犬に適した食事のポイントや、避けるべき食材について詳しく解説します。
- 目次
-
腎臓病の犬に与える食事のポイント
腎臓は老廃物を排出し、体内の水分やミネラルバランスを調整する役割を持ちます。腎機能が低下すると摂取した食事の代謝により生じた老廃物の排出を十分に行えなくなるため、腎臓に負担をかけない食事を与える必要があります。
腎臓病の犬に適した食事のポイントについて、詳しく見ていきましょう。
たんぱく質の過剰摂取を避ける
たんぱく質は犬の筋肉や内臓の健康を維持するために欠かせない栄養素ですが、過剰摂取は腎臓に大きな負担がかかります。
たんぱく質を摂取すると、体内で分解される過程で代謝産物である老廃物が発生し、腎臓によってろ過され尿として排出されます。しかし、腎機能が低下している犬は老廃物の排出がうまく行えず、体内に蓄積されることで腎臓にさらなる負担をかけてしまうだけでなく、全身へも悪影響を及ぼします。
そのため、腎臓病の犬の食事では、たんぱく質の摂取量を適切に管理することが重要ですが、たんぱく質を過剰に制限してしまうと筋肉量の減少や栄養失調につながるため、「良質で適量」が重要です。たんぱく質が多く含まれる食べ物の例としては、牛肉、豚肉、鶏肉、卵、魚、大豆製品などが挙げられます。
リンなどのミネラル含有量を減らす
リン、カリウム、ナトリウムは、いずれも犬の健康維持にとって欠かせないミネラルですが、過剰摂取で腎臓に大きな負担がかかります。
腎機能が低下している場合、体内の老廃物を適切に排出できず、ミネラルが蓄積することで深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。そのため、食事管理においてはミネラル含有量を抑えることが重要です。
ミネラルは、下記のような食べ物に多く含まれています。
-
チーズ(リン・ナトリウムが多く含まれる)
-
ほうれん草(カリウム・リンが豊富)
-
魚卵(イクラ・タラコなど)(リン・ナトリウムの含有量が高い)
ミネラルバランスを適切に管理し、腎臓への負担を軽減することを心がけましょう。
オメガ3脂肪酸を含める
腎臓病の原因の1つは、腎臓の炎症が慢性的に続くことで組織がダメージを受け、正常な機能が失われていくことです。オメガ3脂肪酸には抗炎症作用があり、体内で炎症を抑える働きを持つため、腎臓病の進行を緩和する効果が期待できます。
また、オメガ3脂肪酸には血圧を調整する効果があり、腎臓に負担をかける高血圧の改善にも役立ちます。
オメガ3脂肪酸を多く含む食べ物の例は下記のとおりです。
-
サーモンやマグロ
-
くるみやアーモンド
-
亜麻仁油、しそ油
適量を食事に取り入れることで、腎臓の健康をサポートできます。
食物繊維を含める
腎臓はアンモニアや尿素などの有害物質を体外に排出する役割を担っているため、腎臓の負担を軽減するためには、体内で発生する有害物質の量を抑えることが重要です。食物繊維には腸内環境を整え、有害物質の生成を抑える働きがあります。
食物繊維を多く含む食べ物の例は下記のとおりです。
-
しらたき
-
オクラ
-
オートミール
腸内環境を整えつつ腎臓の負担を軽減するために、食物繊維を食事に取り入れましょう。
腎臓病の犬が食べてはいけない食べ物

腎臓の働きが低下すると、老廃物の排出がスムーズに行えなくなり、体内に有害な物質が蓄積されてしまいます。そのため、腎臓に負担をかける成分を多く含む食べ物はできるだけ避けることが重要です。腎臓病の犬が避けるべき食べ物について詳しく解説します。
高タンパクな食べ物
たんぱく質の過剰摂取は腎臓の負担を増やす要因です。健康な犬にとっては問題がなくとも、老廃物の処理が難しい腎臓病の犬が食べると健康問題につながります。手作りフードを検討する場合は、鳥や魚、大豆などたんぱく質が多く含まれている食材の摂取量を制限し、腎臓の機能に過度な負担がかからないように気を付けましょう。
また、必要なたんぱく質量は腎臓病の進行度や愛犬の体調によって、必要なたんぱく質量は異なるため、獣医師の指導のもとで適切なバランスを維持しましょう。加えて、腎臓病用の療法食は、腎臓に負担をかけにくい形でたんぱく質量が調整されているため、できるだけ専用のフードを選ぶことが大切です。
リンを多く含む食べ物
リンはカルシウムと結合して歯や骨を丈夫にするのに必要なミネラルですが、腎臓病の犬は余分なリンを排出する機能が低下しているため、体内に蓄積されやすくなります。その結果、過剰なリンと結合するためにカルシウムが骨から抜き取られ、骨が弱くなっていきます。高リン食を摂取すると、さらに腎臓に負担がかかり、腎臓病を悪化させる可能性があるため、摂取量を制限する必要があります。リンは殆どの食材に含まれていますが、特にレバーや魚介類、乳製品などに多く含まれているため、これらの食材を与える場合は与える量に注意し、適度な摂取量になるように調節しましょう。
特に加工食品や乳製品の摂取には注意が必要です。
カリウムを多く含む食べ物
腎臓病の犬は、余分なカリウムを排出するための力が低下しています。そのため、高カリウム血症を引き起こし、心臓や筋肉に悪影響を及ぼす可能性があります。高カリウム血症になると、心臓のリズムの乱れや筋肉の異常なけいれん、脱力が起こることがあり、最悪の場合は命に関わります。
ただし、カリウムは腎臓病の進行状況により低くなっていることもありますので、必ず獣医師と相談の上で摂取量を調整するようにしましょう。
カリウムはバナナやほうれん草などの果物や野菜類、海藻類、キノコ類に多く含まれているため、野菜を中心とした食事を与える場合は摂取量に気を付けましょう。
カリウムは茹でることで水に溶け出すため、偏食等の理由でどうしても必要な場合はしっかりと茹でてカリウムを減らしたうえで、獣医師の指導のもと適量を与えましょう。
塩分(ナトリウム)の多い食べ物
ナトリウムの摂取量が多いと血圧が上昇し、腎臓に大きな負担をかけることでさらに腎機能が低下する可能性があります。下記のようにナトリウムが多い食べ物は控えましょう。
-
ハムやベーコン、ソーセージ
-
チーズ
-
味付けされた人間用加工食品
ナトリウムの過剰摂取は腎臓だけでなく心臓にも負担をかけ、高血圧や浮腫(むくみ)を引き起こします。できるだけ薄味の食事を心がけ、加工食品や塩分の多い食材は控えましょう。
腎臓病の犬がごはんを食べないケースがあります。腎臓病用の療法食は通常のドッグフードとは味や香りが異なるため、突然変更すると愛犬が食べなくなることがあります。
そのため、普段食べているフードに少量ずつ混ぜながら、徐々に療法食の割合を増やしていきましょう。
食欲が低下している場合、フードを温めることで香りを引き立たせ、食欲を刺激する効果が期待できます。温める際は電子レンジやぬるま湯を使い、人肌程度の温度に調整するのがポイントです。熱すぎると犬がやけどをしてしまう恐れがあるため、人肌程度の温度に調整し、手で確認してから与えるようにしましょう。
さらに、ぬるま湯や犬用の出汁を加えてドライフードを柔らかくすることも効果的です。腎臓病が進行すると、口内炎や歯のトラブルを抱えやすくなり、硬いフードを噛むこと自体が負担になる場合があります。
また、食べやすくなるだけでなく、水分補給にも役立ちます。腎臓病の犬は脱水症状を起こしやすいため、食事から水分を摂取できるよう工夫することが重要です。
食欲が低下しているときは一度に多くの量を食べるのが難しいため、食事の回数を増やすのも1つの方法です。1回の食事量を減らし、1日に3~4回に分けて与えることで、胃腸への負担を軽減しつつ、総合的な摂取カロリーを確保できます。
犬の状態に応じて適切な方法を選ぶ必要があるため、最終的には獣医師に判断を仰ぎましょう。
腎臓病の犬がごはんを食べないときの対策
腎臓病の犬がごはんを食べないケースがあります。腎臓病用の療法食は通常のドッグフードとは味や香りが異なるため、突然変更すると愛犬が食べなくなることがあります。
そのため、普段食べているフードに少量ずつ混ぜながら、徐々に療法食の割合を増やしていきましょう。
食欲が低下している場合、フードを温めることで香りを引き立たせ、食欲を刺激する効果が期待できます。温める際は電子レンジやぬるま湯を使い、人肌程度の温度に調整するのがポイントです。熱すぎると犬がやけどをしてしまう恐れがあるため、人肌程度の温度に調整し、手で確認してから与えるようにしましょう。
さらに、ぬるま湯や犬用の出汁を加えてドライフードを柔らかくすることも効果的です。腎臓病が進行すると、口内炎や歯のトラブルを抱えやすくなり、硬いフードを噛むこと自体が負担になる場合があります。
また、食べやすくなるだけでなく、水分補給にも役立ちます。腎臓病の犬は脱水症状を起こしやすいため、食事から水分を摂取できるよう工夫することが重要です。
食欲が低下しているときは一度に多くの量を食べるのが難しいため、食事の回数を増やすのも1つの方法です。1回の食事量を減らし、1日に3~4回に分けて与えることで、胃腸への負担を軽減しつつ、総合的な摂取カロリーを確保できます。
犬の状態に応じて適切な方法を選ぶ必要があるため、最終的には獣医師に判断を仰ぎましょう。
腎臓病の犬の食事についてよくある質問

腎臓病の犬の健康を守るために、どのような食材を与えるべきか、また避けるべきかを理解することが大切です。腎臓病の犬に適した食事に関するよくある質問に回答します。
与えても良い野菜の種類は?
腎臓病の犬に与えても良い野菜には、低リン・低カリウムのものが適しています。
たとえば、キャベツやにんじん、カリフラワーなどは比較的安全に与えられる野菜です。茹でて細かく刻むことで、消化しやすくなり、胃腸の負担も軽減できます。ただし、野菜にもカリウムやリンを多く含むものがあるため、与える野菜の種類や量に関しては獣医師に相談しましょう。
与えても良い肉の種類は?
肉類は犬の主なタンパク源ですが、腎臓病の犬にはたんぱく質の摂取量を管理する必要があります。与えても良い肉としては、脂肪分が少なく消化しやすい鶏の胸肉やささみが挙げられます。
鶏の胸肉やささみは適量であれば腎臓への負担を抑えながら栄養を摂取できるでしょう。ただし、摂取量が多い場合は尿毒症を引き起こす可能性があるため注意しましょう。
サプリメントを与えても良い?
サプリメントは、適切な成分を選べば腎臓の健康維持に役立つ可能性があります。
代表的な成分には「吸着・排出サポート成分」「乳酸菌類」「オメガ3脂肪酸」があり、リンの蓄積防止や腸内環境の改善、炎症の抑制、血流改善などが期待されます。
ただし、すべての犬に適しているわけではないうえに、薬との相互作用にも注意が必要です。
安全性の高いサプリメントを選ぶためには、動物病院で取り扱われているものや、成分の含有量が明確なものを選ぶことが重要です。また、食欲が低下しがちな犬には食べやすい形状のものを選ぶと良いでしょう。
サプリメントはあくまで補助的なものであり、腎臓病を治療するものではありません。療法食や適切な医療ケアを中心に、獣医師と相談しながら適切に活用することが大切です。
犬に手作りの食事を与えても良い?
腎臓病の犬に手作りの食事を与えることは可能ですが、栄養バランスの管理が難しいため、おすすめできません。腎臓病の食事管理では、たんぱく質・リン・ナトリウムの制限が重要です。複数の栄養素を適切に調整しながら必要なカロリーやビタミン、ミネラルを確保するのは容易ではありません。
市販のドッグフードや療法食は、腎臓の負担を軽減するよう専門的に調整されていますが、手作り食では必要な栄養素が不足したり、逆に過剰になったりするリスクがあります。
食事療法は効果がある?
動物病院で取り扱われている犬用特別療法食は、犬の腎臓病に適した食事として開発されています。食事療法によって腎臓病を完全に治すことはできませんが、適切な食事管理によって腎臓への負担を軽減し、進行を遅らせる効果が期待できます。
たんぱく質やリン、ナトリウムの摂取量を調整し、腎臓に負担をかけにくい栄養バランスを維持することが重要です。また、オメガ3脂肪酸などの抗炎症成分を含む食事は、腎臓のダメージを抑える働きが期待できます。
食事療法は、腎臓病の進行度に応じて適切な内容に調整する必要があるため、獣医師の指導のもとで進めましょう。
まとめ 腎臓病に配慮して愛犬の食事を管理をしよう
腎臓病の犬には、腎臓への負担を軽減するために適切な食事管理が欠かせません。たんぱく質やリン、カリウム、ナトリウムの摂取量をコントロールしつつ、オメガ3系脂肪酸や食物繊維を含む食品を取り入れることが大切です。また、愛犬の食欲に合わせて食事の与え方を工夫しましょう。
食事療法は自己判断ではなく、獣医師と相談しながら進めることが重要です。愛犬が長く元気に過ごせるように、適切な食事とケアを心がけましょう。
- 監修者プロフィール
-
岩谷 直(イワタニ ナオ)
経歴:北里大学卒業。大学研修医や企業病院での院長、製薬会社の開発や学術職などを経て株式会社V and P入社
保有資格:獣医師免許