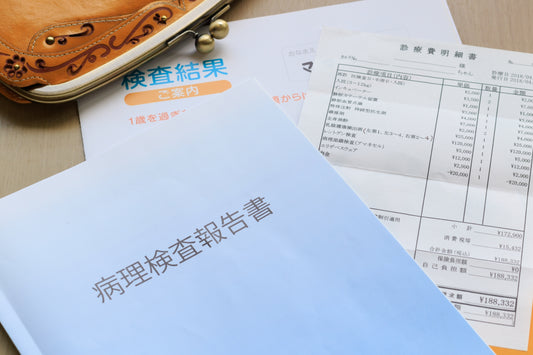【獣医師監修】犬のクッシング症候群とは?症状・原因・治療法などについて

「クッシング症候群」はなかなか聞き慣れない病名であり、戸惑う方も多いかもしれません。獣医師から説明を受けたものの、内容がうまく頭に入ってこなかったというケースもあるでしょう。
そこで本記事では、クッシング症候群の概要、症状、原因や、必要となる検査・治療などについて、分かりやすく解説します。診断後に冷静に状況を理解し、適切な対応を取るための基礎知識として参考にしてみてください。
- 目次
-
犬のクッシング症候群とは?
クッシング症候群は「副腎皮質機能亢進症」とも呼ばれ、犬によく見られる内分泌系の病気です。若齢でもみられる事がありますが、特にシニア期以降に多く見られるため、シニア期に入ったら定期的な健康診断を受け、早期発見と早期治療に努めることが重要です。
この病気で問題となるのは、「副腎」という内分泌器官から分泌される「コルチゾール」と呼ばれるホルモンです。副腎は左右の腎臓の内側に位置し、外側の「副腎皮質」と内側の「副腎髄質」に分かれており、それぞれ異なる複数のホルモンを分泌する「ホルモン工場」のような役割をする器官です。
クッシング症候群は、副腎皮質が分泌するいくつかのホルモンのうち、「コルチゾール量」が過剰になる疾患です。コルチゾールは体内の恒常性を一定に保つさまざまな役割があり、過剰分泌されると、犬の体にさまざまな症状を引き起こします。
本来、ホルモンの分泌量は、他の臓器との密接な連携によりお互いに影響し合って調整されます。副腎皮質からのホルモン分泌が必要な状況になると、以下の流れが生じます。
-
脳の視床下部から、脳下垂体に対して副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)が分泌される
-
CRHを受け取った脳下垂体前葉は、副腎皮質に対して副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)を放出する※ACTHは視床下部に対してCRHの放出を抑制させる働きも持っています
-
ACTHを受け取った副腎皮質はコルチゾールを放出する
※コルチゾールは上位器官に対してACTHやCRHの放出を抑制させる働きも持っています
副腎皮質から分泌されるコルチゾール量の調整には、視床下部と脳下垂体前葉から分泌される上位ホルモンが、このように関与しています。
犬のクッシング症候群の主な症状
クッシング症候群ではさまざまな症状が現れますが、多くは過剰なコルチゾールの分泌によるものです。
比較的多く見られる症状は多飲多尿で、異常なほどたくさんの水を飲んでは、透明に近い薄いおしっこを大量にします。他にも、食欲亢進(食欲が異常に高まり、以前は興味を示さなかった食べ物にも執着するようになることがあります)や体重増加、腹部膨満(腹部の筋肉が弱くなり、「ビール腹」のような状態になります)、皮膚の病変(皮膚が薄くなったり、乾燥してフケが増える、傷が治りにくくなるなど)、パンティング(浅くて速い呼吸)、筋力低下などもよく見られます。
特に初期の頃は食欲亢進による体重増加や多飲多尿が見られますが、進行に伴い筋肉量が低下し、お腹だけが膨れたような体型になっていきます。
皮膚の病変では、皮膚が薄くなる、体に対称性の脱毛が起きる、石灰化による固い結節やえぐれたような欠損(びらん)ができる、皮膚の感染症になりやすいといった、さまざまな症状が現れます。
さらに糖尿病を併発したり、クッシング症候群の原因によっては元気消失、食欲低下、異常行動、失明などの神経症状を伴うこともあります。さらにまれにですが、肺動脈塞栓症による呼吸困難が見られる場合もあります。
高齢になってから発症しやすい病気なので、「歳のせいかも」と勘違いしてしまい、気づかぬうちに進行しているケースもありますので、注意が必要です。
犬のクッシング症候群の原因
クッシング症候群の原因は、大きく分けて3つあります。
-
脳下垂体の腫瘍:下垂体性(PDH)
-
副腎の腫瘍:副腎腫瘍性(ATH)
-
ステロイド剤の投与:医原性
上記の通り、下垂体性(PDH)・副腎腫瘍性(ATH)・ステロイド剤の長期過剰投与による医原性の3つに大別できます。80〜90%はPDH、10〜20%はATHだと言われています。
ここでは、それぞれの原因について詳しくお伝えします。
脳下垂体の腫瘍
通常であれば、視床下部、脳下垂体、副腎が連携してホルモンの分泌量をお互いに適正化するように働きます。しかし、脳下垂体に腺腫と呼ばれる良性の腫瘍ができると、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)が過剰に分泌されてしまうことがあります。
この影響を受け、副腎皮質もコルチゾールを過剰に分泌してしまうようになるのが、下垂体性クッシング症候群(PDH)の原因です。
副腎の腫瘍
先述した通り、ホルモンの分泌量は、上位と下位のホルモンがお互いに影響し合って調整されます。
しかし、上位ホルモンとは関係なく、副腎そのものが腫瘍化することでコルチゾールを過剰に分泌してしまうのが、副腎腫瘍性クッシング症候群(ATH)です。
この場合、視床下部や脳下垂体からは適切な指示のホルモンが分泌されてくるのですが、副腎自身が誤動作を起こして暴走してしまっているような状態なので、必要以上のホルモンを分泌してしまうのです。
ステロイド剤の長期投与による医原性
ホルモンは、化学的な構造によりペプチドホルモン、ステロイドホルモン、アミノ酸誘導体ホルモンの3種に分類されます。副腎皮質から分泌されるホルモンは、コルチゾールも含めてステロイドホルモンに属しています。
コルチゾールなどのステロイドホルモンには抗炎症作用があるため、治療薬として用いられますが、長期的に使用されると体内のコルチゾールレベルが異常に上昇し、クッシング症候群が引き起こされることがあり、これを医原性クッシング症候群と呼びます。
最近は獣医師の間でも医原性クッシング症候群への理解が深まり、しっかりとした投与計画に基づいた治療や投与量の調整が行われているため、医原性クッシング症候群の発生は減ってきています。
犬のクッシング症候群の検査(診断)方法

病気の診断には、広く総合的な検査が必要です。それは、ありとあらゆる病気の中から医師による健康チェックや検査により一つずつ除外できる病気を取り除いていき、最後に残った病気をさらなる検査によって確定的に診断する必要があるためです。
そのため、クッシング症候群の診断にあたっても、身体検査、血液検査、画像検査といった検査を経て確定診断が行われます。
身体検査
獣医師による飼い主さんへの問診が終わると、実際に獣医師が視診・聴診・触診によって外見や心音、呼吸の状態、皮膚病変の有無などをチェックしていきます。
皮膚病変やパンティング、腹部膨満や筋力低下など、類似の症状を示す他の病気などもあるため、この段階で類似した病気を除外しながら絞り込んでいき、確定するために必要な検査項目を決めていくのが一般的です。
例えば多飲多尿の症状がある場合は、尿検査を行って尿比重が低下しているかなどを調べます。
血液検査
赤血球の増加、白血球のストレスパターン、血中の肝酵素の上昇、高脂血症などを確認し、クッシング症候群が疑われる場合は、血中のコルチゾールが増加したことで受ける影響の有無を確認します。
さらに、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)を注射し、血中のコルチゾール量を測定して副腎の反応を調べる「ACTH刺激試験」という検査を実施することがあります。
また、「低用量デキサメタゾン抑制試験」を用いて、ステロイド投与による血中コルチゾール量の変化を調べることもあります。
内分泌学的な検査としては、低用量デキサメタゾン試験がゴールドスタンダードとされますが、国内では簡便に実施できるACTH刺激試験が最も選択されています。
画像検査
副腎は左右の腎臓の内側にある小さな臓器です。小型犬だと3〜5mm、中〜大型犬でも5〜8mm程度のサイズです。
下垂体性(PDH)の場合は両方の副腎が腫大し、副腎腫瘍性(ATH)の場合は片方の副腎だけが腫大していることが多いため、エコー検査で両方の副腎の状態を確認します。
また、コルチゾールは肝臓で行われる糖新生を促進する作用を持つ影響で、クッシング症候群では肝臓が腫大する場合も多いため、合わせて確認します。さらに、全身麻酔等のリスクを考慮して可能と判断された場合は、頭部のCT検査で下垂体の腫大を確認する場合もあります。
犬のクッシング症候群の治療について
クッシング症候群が進行すると、症状の悪化により愛犬に苦しい思いをさせることになります。そのため、クッシング症候群と診断されたら、病気が進行してしまう前に適切な治療を受けさせることが大切です。
ただし、場合によっては難しい治療法もあるため、かかりつけの獣医師とよく相談し、一緒に治療方針を決めていきましょう。
治療法
クッシング症候群の治療法には、外科手術、内科療法、放射線療法があります。原因によって治療方針は異なり、さらにPDHの場合は下垂体の腫瘍の大きさを考慮する必要があります。
(1) 外科手術
下垂体性(PDH)の場合、根治治療は下垂体の切除です。しかし、脳下垂体は脳の奥にあるため非常に高難度な手術となり、実施できる動物病院が限られます。腫瘍の直径が10mmを超える場合には外科手術や放射線治療が第一に検討されることが一般的です。
副腎腫瘍性(ATH)の場合、第一選択肢は副腎の摘出です。副腎は2つある臓器なので、1つを取り出しても残りの1つで賄える可能性があるためです。
しかし、下垂体切除後は必ず、また副腎摘出後も残りの副腎の働きが弱い場合は、共に薬によるホルモンの補充を生涯継続する必要があります。
(2) 内科療法
全身麻酔のリスクなどにより外科手術を適用できない場合は、内科療法を選択するケースが一般的です。
多くの場合、トリロスタンというコルチゾールの合成を抑える薬剤の経口投与を低用量から始めます。コルチゾールの合成を抑制するため下垂体性にも副腎性にも使用が可能です。ただし、トリロスタンには食欲不振、元気消失、下痢、嘔吐等の副作用もあります。飼い主さんと獣医師との連携による、生涯にわたる投薬と愛犬のQOL(生活の質)の維持管理が大切になります。
かつてはミトタンと呼ばれる副腎皮質の細胞を破壊する薬剤も副腎腫瘍に有効とされ使用されていましたが、副作用のリスクのため現在ではトリロスタンが主流となっています。
(3) 放射線療法
下垂体の切除手術を適用できず、かつ下垂体の腫瘍が1cmを超える大きさの場合に適用となることが多い治療法で、放射線の照射により下垂体の腫瘍を小さくする治療法です。ただし、必要な設備が整っている二次診療施設でしか行えない治療です。
治療期間
外科手術の場合、治療期間は入院して手術を行うまでの期間だと考えてしまいがちですが、術後の状態次第では入院管理が必要になることもあります。また、クッシング症候群の場合は、内科療法でも外科手術でも、基本的には生涯にわたる治療が必要になります。
理由は治療法でも述べた通り、摘出した下垂体や副腎を補うためのホルモン投与や、コルチゾールの過剰分泌を抑制するための薬剤投与を継続しなければならないためです。
定期的に動物病院で診察を受け、治療の効果を確認する検査を受けたり、必要に応じて薬の量を調節するなどで、愛犬のQOLの維持に努めましょう。
費用目安
動物病院は、人間の病院の自由診療にあたるため、病院によって費用が異なります。
基本的には、高度な医療設備が整っていたり、獣医師や動物看護師が24時間常駐している病院ほど、費用が高い傾向にあります。高額な外科手術や放射線療法だけでなく、内科療法の場合も、事前に動物病院に確認しておくことをおすすめします。
あくまでも参考ですが、クッシング症候群の内科療法の目安は下記になります。
-
1回あたりの平均診察料=13,500円程度
-
平均年間通院回数=6回程度
※ただし検査費用は別途必要になります
犬のクッシング症候群についてよくある質問

犬のクッシング症候群についてよく寄せられる質問をご紹介しますので、参考にしてみてください。
予防法はある?
クッシング症候群に対する予防法は、基本的にはありません。
唯一あるのは、医原性のクッシング症候群のみです。アトピー性皮膚炎や免疫介在性溶血性貧血などの治療として、ステロイドホルモンを投与することがあります。その際に、適切な投与計画を立て、かつ適切な管理により投与の中止や減量を行うことで、医原性クッシング症候群の発症を予防できることがあります。
かかりやすい犬種は?
基本的には、高齢になるとどの犬種でも発症しやすい病気で、特に好発発犬種はありません。
ただし、日本ではトイ・プードル、ミニチュア・ダックスフンドに多く見られるという報告もあるようです。該当犬種に限りませんが、飼い主さんは愛犬の飲水量や食欲、体重の変化や、尿の状態や量の変化には、常に気をつけて観察しておくことをおすすめします。
自宅でできるケアは?
クッシング症候群の愛犬に対して飼い主さんがご自宅でしなければならないケアには、下記が挙げられます。
-
確実な投薬管理(自己判断で勝手にやめたり量を変えたりしない)
-
愛犬の体調変化の早期察知(特に副作用が出ていないかについての注意が必要)
-
体調管理(薬の副作用で免疫力が低下するため、日々の観察が欠かせません)
-
食事管理(通常の食事管理の他に、クッシング症候群特有の管理も必要)
特に食事管理に関しては、クッシング症候群の犬で控えるべきものがあります。
下記の記事も参考に、しっかりと食事管理をしてあげましょう。
- 関連記事:
-
【獣医師監修】クッシング症候群の犬が食べてはいけないものとは?食事管理のポイント
まとめ 犬のクッシング症候群は早期発見が大切
犬のクッシング症候群は、早期発見、早期治療がとても大切です。最初は多飲多尿や食欲増進といった症状のため、「元気だ」と見過ごしてしまわれる場合もありますが、病気が進行するにつれ、愛犬はどんどん苦しい状態になっていきます。
特にクッシング症候群は、生涯付き合っていかなければならない病気です。できるだけ早く発見し、適切な治療を開始することで、愛犬の負担を軽くし、できるだけ健康を維持してあげられるようにしてあげましょう。
- 監修者プロフィール
-
岩谷 直(イワタニ ナオ)
経歴:北里大学卒業。大学研修医や企業病院での院長、製薬会社の開発や学術職などを経て株式会社V and P入社
保有資格:獣医師免許