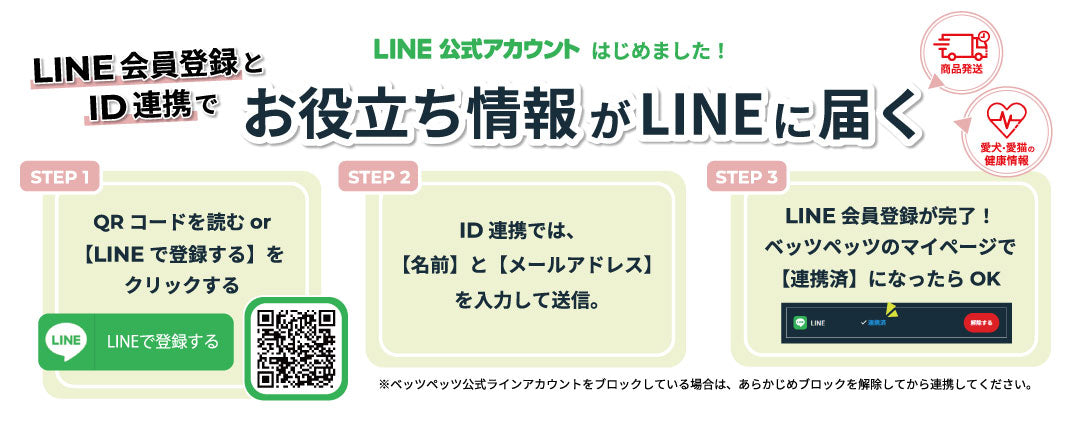【獣医師監修】猫の皮膚糸状菌症とは?原因・症状・治療法などについて解説

猫の皮膚に突然あらわれた脱毛やフケ。「もしかして皮膚疾患?」と不安になる飼い主さんも多いのではないでしょうか。
その症状、もしかすると「皮膚糸状菌症」かもしれません。
皮膚糸状菌症は、真菌(カビ)の一種によって起こる感染症で、人にも感染するおそれのある病気です。子猫や高齢猫、免疫力が落ちている猫はかかりやすく、早期の対応が欠かせません。
本記事では、猫の皮膚糸状菌症の原因・症状・診断法・治療法・予防策に加えて、人への感染リスクについても詳しく解説します。
- 目次
-
猫の皮膚糸状菌症とは?
猫の皮膚糸状菌症は、真菌によって引き起こされる皮膚感染症です。
主に、「Microsporum canis(ミクロスポルム・カニス)」という真菌によって引き起こされます。体力や免疫が弱っている子猫や老猫では、発症リスクが高まります。
Microsporum canisは空間内でも長く生き残り、感染力を保ち続けるため、症状の治療とあわせて、生活環境の清掃・除菌も重要です。
猫の皮膚糸状菌症とは?
猫の皮膚糸状菌症は、真菌によって引き起こされる皮膚感染症です。
主に、「Microsporum canis(ミクロスポルム・カニス)」という真菌によって引き起こされます。体力や免疫が弱っている子猫や老猫では、発症リスクが高まります。
Microsporum canisは空間内でも長く生き残り、感染力を保ち続けるため、症状の治療とあわせて、生活環境の清掃・除菌も重要です。
猫の皮膚糸状菌症の原因

猫の皮膚糸状菌症は、「Microsporum canis(ミクロスポルム・カニス)」や「Trichophyton mentagrophytes(トリコフィトン・メンタグロフィテス)」といった真菌の一種によって引き起こされます。
毛や爪、皮膚に含まれるケラチンというタンパク質に取りついて増殖します。また、環境中の毛やフケのかけらなどを介しても広がりやすく、感染した猫の生活空間全体が汚染されるおそれがあります。したがって、治療とあわせてこまめな掃除や消毒も重要です。
感染ルートとして最も多いのは、ほかの動物との接触です。また、真菌が付着した寝具・ブラシなどを介した間接的な接触によって感染する場合もあります。
なかには自覚症状のない「キャリア」の猫も存在し、見た目に異常がなくても病原菌を持っている場合があります。キャリアと接触することで、知らないうちに感染が広がることも少なくありません。
多頭飼いの家庭や、外出する機会が多い猫は、接触や環境汚染のリスクが高いため注意が必要です。
猫の皮膚糸状菌症の症状
皮膚糸状菌症にかかった猫は、主に次のような症状が見られます。
-
円形・斑状に毛が抜ける脱毛(境界が比較的はっきりしていることが多い)
-
毛の断裂(被毛が皮膚表面で折れて短くなる)
-
フケが目立つようになる
-
赤みを帯びた皮膚の炎症
-
表面にできるかさぶた
頭や耳、足先などによく見られ、子猫では症状が強く出やすい傾向があります。日頃から猫の体に触れ、脱毛や皮膚の異常がないかをチェックすることが大切です。症状が見られたら、早めに動物病院を受診しましょう。
猫の皮膚糸状菌症の診断方法

皮膚糸状菌症の診断に必要な情報を集めるために、視診のほかに複数の検査を行います。
症状だけでは他の皮膚疾患と区別がつきにくいため、正確な診断と適切な治療には検査が欠かせません。以下に代表的な検査方法を紹介します。
ウッド灯検査
ウッド灯という特殊な紫外線ライトを使い、暗い環境下で猫の被毛を照らして感染毛の特徴的な緑黄色の発光を観察します。
皮膚糸状菌症の原因となる真菌のMicrosporum canisやM. ferrugineum 、M. gypseum によるものの一部については検体が緑黄色に発光するため、診断に役立ちます。フケや軟膏などの付着物に偽陽性を示すこともあるので判断には注意が必要です。
ウッド灯検査だけで判断するのではなく、疑わしい場合は他の検査も併用するのが基本です。
毛検査
ウッド灯陽性部位や皮膚の病変の周囲から被毛を数本採取し、顕微鏡で観察する検査です。感染している場合は、被毛にカビの胞子や菌糸が付着していたり、毛が太く不自然な形に変化していたりします。迅速かつ低コストで行えるため、初期検査としても有用です。
真菌培養検査
採取した被毛や皮膚片を専用の培地に移し、カビの発育状況を観察する検査です。菌の種類や特徴的な色の変化をもとに診断を行います。結果が出るまでに2〜3週間ほどかかりますが、診断精度は高く、感染の確定に有効です。
一般的な検査としてはここまでです。以下の検査は診断が難しい場合の鑑別診断や、病変部位をより詳細に確認したい場合に行われることがあります。
PCR検査
PCR検査では、猫の被毛から採取したサンプル内に皮膚糸状菌のDNAが存在するかどうかを直接調べます。遺伝子を検出するため、感度が高く、診断精度の向上に役立つ検査です。
感染の有無が他の検査で判断しづらいときにも活用でき、迅速で感度は高いですが、すでに死滅した菌の遺伝子も検出されるため、治療効果判定のモニタリングには推奨されず、皮膚の状態や他の検査結果とあわせた総合的な評価が求められます。
皮膚病理検査
皮膚病理検査は、真菌が皮膚の深層にまで達して炎症性の結節を呈している疑いがある稀なケースで実施されることがあります。病変部を少量採取し、顕微鏡で組織構造を詳しく観察することで、感染の範囲や炎症の程度などを明らかにできます。
慢性化している皮膚症状や、通常の検査でははっきりと診断できない場合に用いられることがあり、他の皮膚疾患との鑑別にも役立つ検査です。
猫の皮膚糸状菌症の治療法
猫の皮膚糸状菌症は、完治までに時間がかかることもある皮膚疾患です。治療は主に「内服薬」と「外用薬」の併用が基本で、加えて環境整備も欠かせません。猫自身だけでなく、周囲の動物や人への感染リスクもあるため、総合的な対策が必要です。猫の皮膚糸状菌症の治療法について詳しく見ていきましょう。
抗真菌薬の内服
皮膚糸状菌症の中心的な治療法が、抗真菌薬の内服です。イトラコナゾールやテルビナフィンといった薬剤の数週間〜1ヶ月程度の継続投与が基本です。場合により、イトラコナゾールは1週間の投与と1週間の休薬を1サイクルとして3~4サイクル行われることもあります。症状の範囲や深さによっては、それ以上の治療期間が必要となることもあります。
内服薬は、体内から真菌を抑える効果がある一方で、吐き気や下痢、肝機能への影響といった副作用に注意が必要です。定期的な診察や血液検査などを行いながら、獣医師と相談して投与量や間隔を調整します。
外用療法
症状が軽い場合や局所に限られる場合は、外用薬のみでも治療できる可能性があります。塗布タイプの抗真菌薬(クリームやローション)を患部に直接塗ったり、抗真菌成分を含む薬用シャンプーで全身を洗浄したりします。
全身に症状が広がっている場合は、シャンプーによる洗浄が効果的です。皮膚表面に存在する真菌を減らし、再感染や他への拡散を防ぐ目的でも役立ちます。内服治療と外用療法を組み合わせることで、治癒率を高めることができます。
環境対策
皮膚糸状菌は、皮膚や被毛から落ちたフケなどにも存在し、環境中でも長期間生存します。そのため、感染した猫だけでなく、下記のような生活環境の清掃・消毒が再感染や拡大防止に極めて重要です。
清掃……落ちた被毛やフケは感染源になるため、こまめに掃除機や水拭きを行いましょう。取り切れない部分はコロコロなどを使って丁寧に除去します。
布製品の洗濯……シーツやタオルなど、猫と接触する布類はこまめに洗濯します。
フィルター類の清掃……エアコンや空気清浄機のフィルターも汚染源となりうるため、定期的に清掃しましょう。
消毒……可能であれば塩素系消毒剤を使いますが、屋内素材への影響を考慮して使用箇所は限定します。皮膚糸状菌に対応した消毒剤の使用については、獣医師への相談をおすすめします。
隔離……多頭飼育の場合、感染した猫は他の猫と分けて飼育し、キャリア状態の同居動物も検査・治療対象とすることが推奨されます。
猫の皮膚糸状菌症の予防策
皮膚糸状菌症を防ぐには、まず感染源との接触を避けることがポイントです。とくに野良猫や外出の多い猫との接触、感染歴のある動物との同居などは注意が必要です。
多頭飼育の場合は、感染猫が見つかった時点で隔離し、他の猫への接触を制限しましょう。キャリア(無症状感染)状態の猫も存在するため、症状がなくても念のため定期的な健康チェックを行うことが安心につながります。
また、脱毛や赤み、かさぶたなど皮膚の異常を早期に発見するために、日頃からスキンチェックを習慣化することも重要です。とくに子猫や免疫力が低下している猫はリスクが高いため、こまめな観察を心がけましょう。
さらに、糸状菌は被毛やフケを介して周囲に広がるため、次のような室内環境の衛生管理も欠かせません。
-
掃除機がけや水拭きを定期的に行い、落ちた被毛やフケをこまめに除去する
-
布製品(タオル、毛布など)の洗濯も定期的に実施する
-
エアコンや空気清浄機のフィルター清掃も忘れずに
皮膚糸状菌症は一度発症すると治療に時間がかかるため、日々のケアを大切にし、少しでも異変を感じたら早めに獣医師に相談しましょう。
猫の皮膚糸状菌症は人に感染する?

猫の皮膚糸状菌症は、人にも感染するリスクがある「人獣共通感染症」です。猫の症状が軽度であっても、抜け毛やフケ、皮膚に付着した真菌の胞子が家具や寝具に付着し、人間がそこから感染してしまうケースも少なくありません。
子どもや高齢者、免疫力が低下している人は、感染すると症状が出やすく、悪化しやすい傾向があります。皮膚に赤みやかゆみ、円形の発疹が見られた場合には、「白癬(はくせん)」や「リングワーム」などの名称で診断されることがあり、皮膚科での早期受診と治療が大切です。(猫と人の「リングワーム」は同じカテゴリーの疾患(皮膚糸状菌症)であり、原因菌が一部重なる(特にMicrosporum canis)ため、猫から人にうつることがあります。ただし、人で最も多い白癬菌(Trichophyton rubrum)は猫では稀です。)
感染のきっかけはさまざまで、主に以下のような感染経路が挙げられます。
-
感染した猫をなでた手で顔や体に触れる
-
猫のフケや被毛が付着した毛布やソファなどに触れる
このように、人への感染は「直接的」だけでなく「間接的」にも起こるため、感染が疑われる猫の治療とあわせて、清潔な環境を保つことも不可欠です。
猫の症状があるときは素手での接触を避ける、接触後は石けんと流水で手を洗う、家族の中に皮膚トラブルが出たら早めに皮膚科を受診するといった対応を心がけましょう。
皮膚糸状菌症は適切な治療で治癒が見込めるため、猫も人も早期発見・早期対応が重要です。
まとめ 猫の皮膚糸状菌症は早めに動物病院へ
猫の皮膚糸状菌症は、見た目の変化に気づきにくい皮膚疾患でありながら、人間にも感染する可能性のある注意すべき病気です。
脱毛やフケ、赤みなどの初期症状を見逃さず、早めの診断と治療につなげることが、猫の健康を守ることにつながります。
治療には内服薬と外用薬の併用が基本で、あわせて生活環境の清掃・消毒や感染対策も重要です。また、多頭飼育や外出習慣がある猫では再発・感染拡大のリスクも高いため、予防的なケアと日常の観察習慣を心がけましょう。
猫の健康だけでなく、家族全員の安心のためにも、気になる症状があれば早めに動物病院を受診してください。
- 監修者プロフィール
-
岩谷 直(イワタニ ナオ)
経歴:北里大学卒業。大学研修医や企業病院での院長、製薬会社の開発や学術職などを経て株式会社V and P入社
保有資格:獣医師免許